| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石田三成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 近江の国坂田郡石田村(現・滋賀県長浜市石田町)出身。 父・正継(藤左衛門)の次男・佐吉として生まれる。(石田氏はこの地の土豪であった可能性もあるらしい) 羽柴秀吉の長浜城主時代に、父、兄・正純と共に仕官したとされる。(三成が15〜18歳の頃) 秀吉が鷹狩りに出かけたときに三杯のお茶を出したエピソードが、三成召し抱えの逸話(「武将感状記」という1716年の書物が初出とされている)として語られることがあるが、この話は後年の作り話の可能性が高い。 「茶道四祖伝書」に同じような逸話(登場人物は千利休と後の土屋喜斎となる小僧)があるらしい。
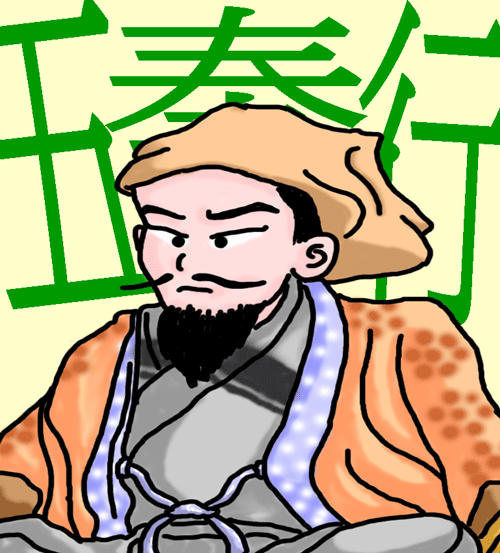 秀吉に召し抱えられた三成は、中国攻めに従軍する。 その後、本能寺の変が起き、秀吉が天下の階段を登っていく脇を固める一人として台頭していく。 1583年(天正11年)の賤ケ岳の戦いでは先駆け衆として一番槍の功をあげた。 1586年(天正14年)には、島左近(清興)を召し抱えられるほどの出世をあげている。(島右近の召し抱えについては、三成は自分の知行の半分を与えて召し抱えたという話もある) 堺奉行を命じられ、堺を兵站基地として整備。1587年(天正15年)の九州平定の機動力になったと思われる。 博多奉行として、平定後の九州を整備。 1590年(天正18年)の小田原征伐では、館林城、忍城攻略を命じられる。 1592年(文禄元年)、文禄の役(朝鮮出兵)では渡海して総奉行を務める。 1595年(文禄4年)、佐和山城城主となる。 1597年(慶長2年)、慶長の役(第二次朝鮮出兵)では国内に留まり後方支援を行った。 現地からの状況報告を受けた秀吉が激怒し、一部の大名が処分されるという事件が起きる。報告を行ったのは福原長堯(正室は三成の妹)らであったが、処分を受けた黒田長政、蜂須賀家政らは、福原と三成が秀吉に進言したことで処分が下ったと判断する。このことにより、武断派(加藤清正、福島正則、黒田長政、蜂須賀家政など)と文治派(石田三成、大谷吉継、小西行長など)の間に亀裂が入り、しだいに深まっていく。
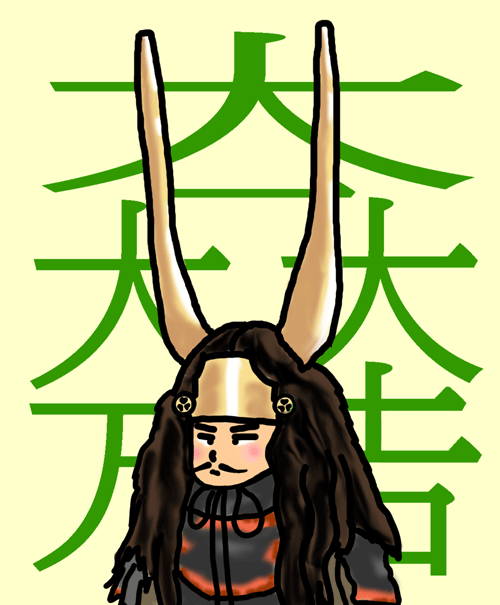 1598年(慶長3年)8月、秀吉が没すると朝鮮へ出兵している軍の帰還業務に尽力する。 1599年(慶長4年)3月、武断派と文治派の対立の調停を仲裁していた前田利家が没すると、その直後、加藤清正、福島正則、黒田長政、細川忠興、浅野幸長、池田輝政、加藤嘉明が三成の大阪屋敷を襲撃するといった事件が起きる。家康が仲介に入り、三成が隠居することになる。 1600年(慶長5年)、家康と武断派武将が会津征伐に出立すると、毛利輝元を大将とする対家康の西軍が挙兵する。この西軍の主軸が三成だとされる。 西軍の大将・輝元は大阪城に詰め、三成を含めた軍勢は東へ進軍。伏見城、伊賀上野城、安濃津城、松坂砂などを落とす。東軍が西上したことを知ると、転進し美濃方面へ向かう。そして、関ケ原の戦いとなる。 小早川秀秋、脇坂安治らが裏切り、西軍が総崩れとなると三成は戦場を脱出する。 9月18日には居城の佐和山城が陥落。 9月21日、逃走していた三成が古橋で潜伏しているところを田中吉政の手の者によって捕縛される。 9月22日、大津城に護送され、城門前で生き晒しにされる。 9月27日、大阪に護送。 9月28日、小西行長、安国寺恵瓊らと共に大坂、堺を罪人として引き回される。 9月29日、京都へ護送。 10月1日、家康の命により六条河原で斬首され、41年の生涯を終えた。その首が晒された後、遺体は京都大徳寺の三玄院に葬られた。 |
■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石田三成の子たち 長男・重家 関ケ原の戦い(1600年/慶長5年)の後に佐和山城が落城する。その際、出家し妙心寺寿聖院に入る。 宗亨(そうきょう)と名乗っていたが、1623年(元和9年)(40歳の時)に済院宗亨大禅師となり寿聖院三世を継承する。 1665年(寛文5年)、住職を弟子に譲り82歳で隠居。 隠居後に石田家の記録などを記すなどして、1686年(貞享3年)に103歳で天寿を全うする。 次男・重成 関ケ原の戦い(1600年/慶長5年)時までは、豊臣秀頼の小姓として大阪城にいたとされる。西軍が敗北となったため、津軽(弘前)藩初代藩主・津軽為信の嫡男・信健に匿われて津軽氏の直轄地(現・弘前市)に逃れる。 津軽では、杉山源吾を名乗り、深味村(現・板柳町)に隠棲する。(杉山八兵衛と名を変えて津軽藩の侍大将となったとする話もあるらしい) 重成の長男・吉成は二代目津軽(弘前)藩主・津軽信枚(つがるのぶひら)の娘を妻にもらい受け、津軽(弘前)藩の家老職として仕えたという。 またその子孫は、弘前藩の重臣として仕えたという。 青森県弘前市の宗徳寺は杉山家の菩提寺であり、その墓には代々「豊臣姓」が刻まれているという。(明治期の子孫の中には豊臣に改姓した者もいるらしい。石田に改姓した者もいそうな気がする) 三男・佐吉 佐和山城落城の際に、三成の兄・正澄の家臣である津田清幽(つだきよふか)に伴われ助命される。 高野山で出家し、深長坊清幽(しんちょうぼうせいゆう)を名乗る。河浦山薬師寺(現・山梨県)の十六世住職となり82歳で没する。 長女 石田家家臣・山田勝重に嫁ぐ。 佐和山城落城(1600年/慶長5年)のとき、夫・勝重(当時25歳)は父・山田上野介からの厳命を受け、妻と嫡男・宇吉郎(5歳)を連れて脱出。(おそらくお付きの者も数人いたであろう)上野介は佐和山城で自害。 どういった経緯からなのか夫・勝重は逃れた先の松平忠輝に仕える。その経緯というのもまた複雑・・・
夫・勝重が忠輝に召し抱えられた経緯は、豊臣秀吉の正室・高台院(北政所/おね)付きの筆頭上臈(ひっとうじょうろう)・孝蔵主(こうぞうす)が茶阿局のもとに送り届けたからだと言われている。
夫・勝重の父・上野介の妹・茶阿局が忠輝の母(徳川家康の側室)だったことから、その縁を頼ったのだと思われる。 佐和山城から逃がすときに「茶阿局はお前の叔母だから頼りなさい」と言ったとか、そういった内容の書状を持たせたとかした上で孝蔵主に託したのかもしれない。 1609年(慶長14年)には、夫・勝重は松代藩の重臣に起用される。 1616年(元和2年)に松平忠輝が改易されると、二代目津軽(弘前)藩主・津軽信枚の正室となっていた妹・辰姫の縁で津軽(弘前)藩から150石を拝領しながら江戸で生活した。夫・勝重は隠棲し山田草山と名乗ったらしい。 1647年(正保4年)、69歳で没する。(1655年5月17日没/77歳 とする説もある) 長男の山田武兵衛は改名して富岡武兵衛と名乗る。そして、津軽信枚の娘・松姫を妻に迎える。 次女・小石殿 蒲生家家臣・岡重政(半兵衛)の室となるが、1613年(慶長18年)に夫・重政は蒲生家の御家騒動の咎で切腹処分(幕府から江戸に呼び出されたとも、家康直々に駿府へ呼び出されたとも言われている)となってしまう。 夫・重政を失った後、会津を離れ若狭国へ移り小浜で没した(没年不明)とされる。
三女・辰姫(辰子/大館御前/荘厳院) 1591年/(もしくは1592年)産まれ。 早い時期から北政所(おね/高台院)の養女になる。秀吉が没したのが1598年。その後らしいので、6〜8歳ごろに養女になったとみられる。 津軽氏の直轄地(現・弘前市)に移ったのが、関ケ原の戦い(1600年/慶長5年)の直後に兄・重成と共に逃げたのか、1610年(慶長15年)の輿入れのときなのかは不明。 いずれにせよ、1610年(慶長15年)に二代目津軽(弘前)藩主・信枚の正室となったようだ。 しかし、1613年/慶長18年(1611年/慶長16年の説もあり)に徳川家康の養女・満天姫(まてひめ/家康の異父弟・松平康元の娘)が、天海大僧正の進言もあって正室として輿入れすることになり、辰姫は側室に降格されてしまう。
関ケ原の戦いにおいての論功行賞として津軽(弘前)藩は、上野国大舘(現・群馬県太田市)に飛び地を得ていた。そこに辰姫は移され、大館御前と呼ばれるようになる。 夫・信枚は参勤交代の折には必ず辰姫のもとに立ち寄った。 1619年(元和5年)には長男・平蔵(のちの信義)が産まれている。 1623年(元和9年)、上野国大舘の地で辰姫(32歳)はその生涯を閉じる。 辰姫が産んだ平蔵(信義)は津軽家三代目当主となる。
その他、三成には複数の側室との間に産まれた子が数人いたという話が、その子孫たちに伝承されているらしい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
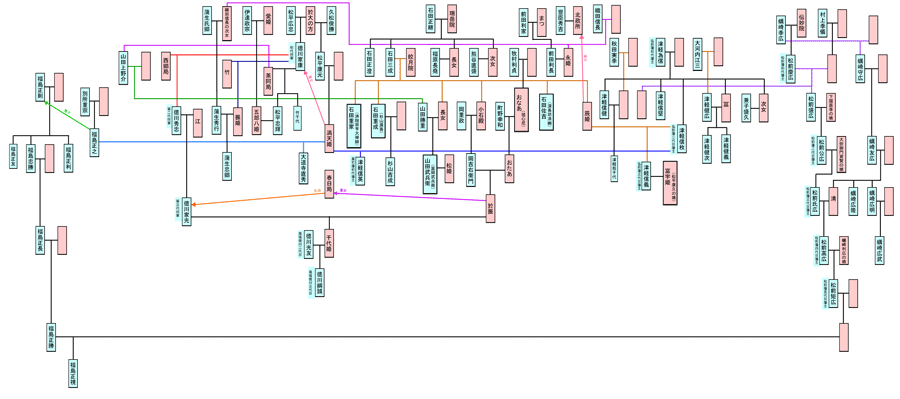 石田三成の子孫の系図(図をクリックすると大きい図が別窓で表示されます) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まあまあ、ここでも同じ名前、似たような名前が錯綜するおかげで分かりにくいったらありゃしない! ○○の子孫に伝わる伝承やらなんやら。どこまで信じられるものやら・・・。 そんな気にもなってしまう。 それにしても、「三杯のお茶」だけではなく、青森(とくに津軽)と石田家(三成の子ら)の繋がりの複雑なことw 南部家から袂を分けて独立した津軽為信が、地盤固めと対南部を考えて、西日本制覇後に北条征伐に動き出した巨大勢力の豊臣秀吉との繋がりを求めたことから始まったと思われる。 本州の端(当時でいえば日本の端)の地とはいえ、日本の中心地(当時の京都)の情報は貿易船からももたらされていたであろう。古くから北海道の海産物は、日本海の各港を経由しつつ最南は沖縄まで至っていたらしいので、津軽半島にも寄港は数か所あってもおかしくはない。十三湊(十三湖)、鰺ヶ沢、深浦とその辺から情報は伝わっていたのではないか?忍者を召し抱えていたという史料もあるらしいので、各地域の情報は集められていたのだと思われる。 そんな中で、「秀吉さ逆らうのはまいね。まんずまいね。へば、へぐ、けやぐさしてもらったほうがいいべね。(秀吉に逆らうのはダメだな。本当にダメだ。それなら、早く仲間にしてもらったほうがいいな)」とか考えて取り入ったのかも。鷹狩りが好きと聞きつけて鷹を献上した話が伝えられている。 秀吉に恭順する流れで三成に繋がりを持ち、徳川にも繋がりを持って、関ケ原の戦いのときには東軍に属しつつ、西軍の主軸である三成の子らを保護することで、東軍対西軍の戦いの結果がどっちに転んでも何とかなるように策を打ったんじゃないかなぁ。他家でもそういった動きがみられたように。 兎にも角にも、青森という地は不思議な地であるなぁ。と、改めて思う私であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年10月 記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2003〜 黒麒燃魂 All Rights Reserved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

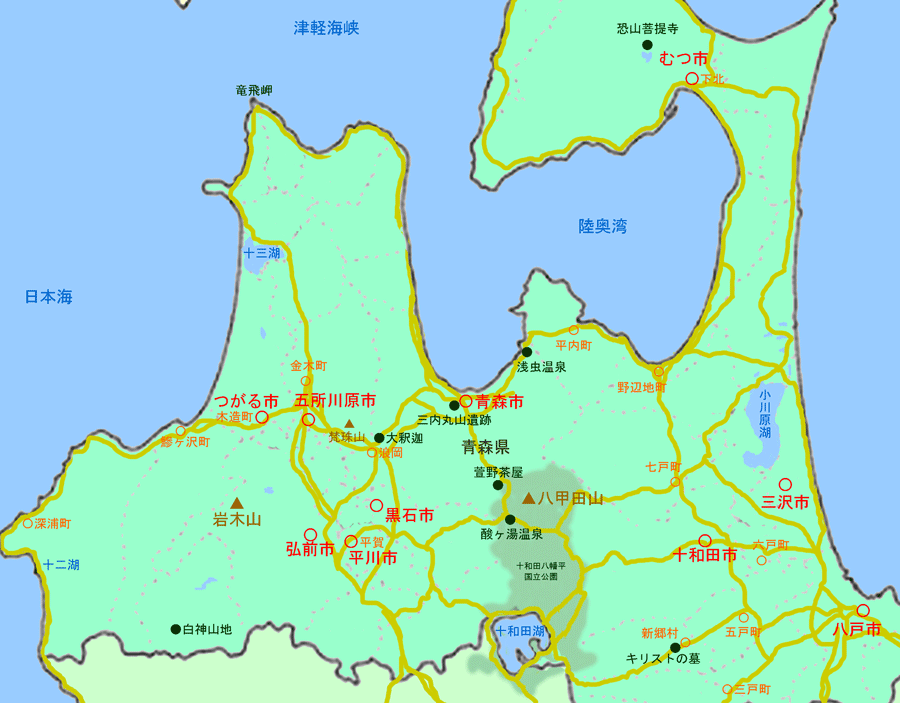
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d3928ef.096b6394.1d3928f0.ea5b13a6/?me_id=1211333&item_id=10005605&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuzukien%2Fcabinet%2F03720024%2Fimg65854211.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b286f6b.ce07e074.0b286f6e.ffa6a4a9/?me_id=1213310&item_id=15831303&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4705%2F9784883254705.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)