| ���j | |||||||||
��ʐ�Ł@�^�@Mass extinction �@ |
|||||||||
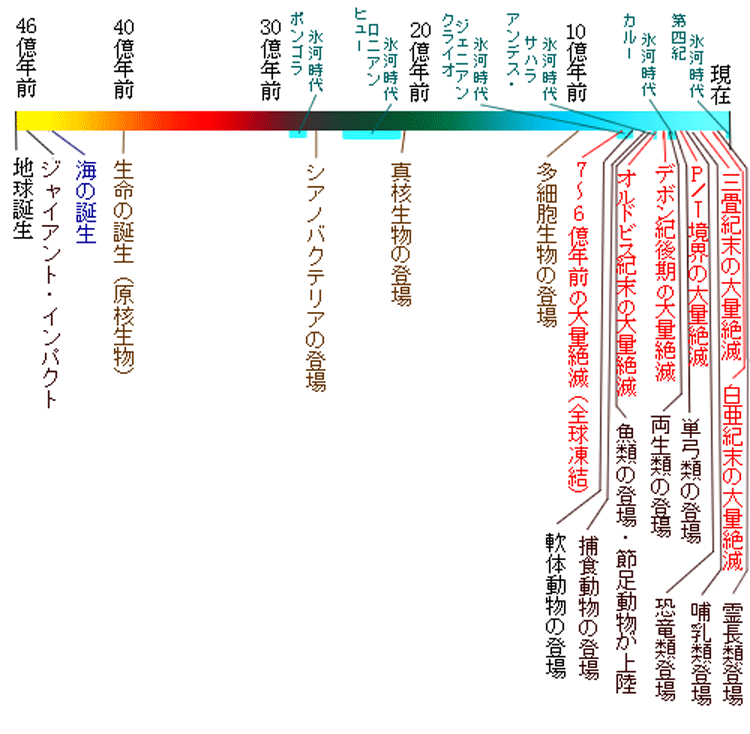 �@ |
|||||||||
| �� | �n����ɐ��������܂�Ă��猻�݂Ɏ���܂ŁA���͐����̐�ł̊�@�����������Ƃ��m�F����Ă���B ���̐�5��ȏ� ��������̐����̂��A���̋��n�����т��������ŁA���̋L�������Ă��邠�Ȃ������̋L���������Ă��鎄�����݂��Ă���̂ł���B �Ȃ�Ƃ܂��A�悭�������c���Ă��̎�i���j�𑶑������Ă��ꂽ���̂ł���B �@ |
�� | |||||||
| �� | �N���C�I�W�F�j�A���X�͎���̑S�������i�X�m�[�{�[���A�[�X�j �@7��2000���N�O�`6��3500���N�O�@�i8��5000���N�O�`6��3000���N�O�@�Ƃ����������j �@ |
�� | |||||||
| �����̎��ŋK�� �@ |
�` | 85�������� | |||||||
| ���̎���̐��� �@ |
�` | �P�זE�����A���זE���� | |||||||
| ���̎����� �@�@�@�@�嗤�� �@ |
�` | �ԓ��߂��Ƀ��f�B�j�A���嗤���`������Ă����Ƃ���� | |||||||
| ���� | �` | 1.�n���S�̂��قڕX�i�X���E�X�C�j�ɕ���ꂽ���� ���������s�������̌����ɂ���C���̓�_���Y�f�Z�x���ቺ �������ʂ���������Ă������≻���n�܂� �X�������B����ɂ��������đ��z���˂��銄�����������A���≻���������Ă����� �i���z�̊����͂����݂����Ⴉ�������߁A�n�����ł̓������g���ʂ��Ⴉ�����Ǝv����j �Ƃ����������� �@ |
|||||||
| �� | �I���h�r�X�I�� �@4��4310���N�O�`4��3100���N�O���� �@ |
�� | |||||||
| �����̎��ŋK�� �@ |
�` | 85�������� | |||||||
| ���̎���̐��� �@ |
�` | �O�t���A�I�E���L�A���ށA�T���S�Ȃ� | |||||||
| ���̎����� �@�@�@�@�嗤�� �@ |
�` | ���݂̓�Ɉ�ɂ������ł��낤�Ƃ���Ă��� | |||||||
| ���� | �` | 1.���V�������i�K���}���o�[�X�g�j�̉e�� 2.�ΎR�����̌��� 3.���̌��� �n���̊��≻�E���g���������ċN����A�X�͂����B�E�X�� ���̂��߂ɁA�C���ʍ���ϓ����N����A���ω��ɑΉ��ł��Ȃ�������������ʂɎ��ł��� �@ |
|||||||
| �� | �f�{���I��� �@3��7400���N�O �@ |
�� | |||||||
| �����̎��ŋK�� �@ |
�` | 82�������� | |||||||
| ���̎���̐��� �@ |
�` | �����A�T���A�b�h���Ȃ� | |||||||
| ���̎����� �@�@�@�@�嗤�� �@ |
�` | ���݂̓�Ɉ�ɂ������ł��낤�Ƃ���Ă��� | |||||||
| ���� | �` | 1.���̌��� ���≻�ƊC�m���_�f���� 2.覐̏Փ� �y�x���M�[�z �y�����암�z ��L�ӏ����珬�V�̏Փ˂̍��Ղ���������Ă���`���̂Ƃ��됶����łƂ̊֘A�͕s���` �@ |
|||||||
| �� | �y���������@PT���E�`Permian�i�y�����I�j-Triassic�i�O��I�j boundary�i���E�j�` �@2��2500���N�O �@ |
�� | |||||||
| �����̎��ŋK�� �@ |
�` | 90���ȏオ���� | |||||||
| ���̎���̐��� �@ |
�` | �����ށA�P�|�ށA�����A���ނȂǁi���ł��C�������̔�Q���傫�������Ƃ����j | |||||||
| ���̎����� �@�@�@�@�嗤�� �@ |
�` | �قڂ��ׂĂ̑嗤���ꂩ���ɏW�܂�����Ԃ̃p���Q�A���嗤�̎��� | |||||||
| ���� | �` | 1. 覐̏Փ� �y�I�[�X�g�����A�z �y��ɕt�߁z ��L�ӏ����珬�V�̏Փ˂̍��Ղ���������Ă��� 2.�ΎR�����̌��� �}���g���Η��̗��ꂩ��������ς��A�ΎR�������������� 3.���̌��� ���≻�ɂ��C�ʌ�ނ��N���ĐH���A���̃o�����X���傫�����ꂽ �@ |
|||||||
| �� | �O����� �@2���N�O �@ |
�� | |||||||
| �����̎��ŋK�� �@ |
�` | 76�������� | |||||||
| ���̎���̐��� �@ |
�` | ��ށA�P�|�ށi��Łj�Ȃ� | |||||||
| ���̎����� �@�@�@�@�嗤�� �@ |
�` | �p���Q�A���嗤�����吼�m���`������� | |||||||
| ���� | �` | 1.�ΎR�����̌��� ��K�͂ȉΎR���� 2.覐̏Փ� �y�J�i�_�A�P�x�b�N�B�̃}�j�N�A���K���E�N���[�^�A�}�j�g�o�B�̃Z�C���g�E�}�[�e�B���E�N���[�^�[�z �y�t�����X�A���V���V���[���E�N���[�^�[�z �y�E�N���C�i�A�I�{�����E�N���[�^�[�z �y�A�����J�A�m�[�X�E�_�R�^�B�̃��b�h�E�E�C���O�E�N���[�^�[�z ���������Ă��� �j�ӂ����V�́i���a3.3�`7.8�q���x�j���������ɗ����i�Փˁj�����Ƃ���� 3.���≻�ƊC�m���_�f���ςɂ����� �@ |
|||||||
| �� | �����I�� �@6550���N�O �@ |
�� | |||||||
| �����̎��ŋK�� �@ |
�` | 70�� | |||||||
| ���̎���̐��� �@ |
�` | �����i�قڐ�Łj�A��ނȂ� | |||||||
| ���̎����� �@�@�@�@�嗤�� �@ |
�` | �p���Q�A���嗤��6�嗤�ւƕ��Ă��� | |||||||
| ���� | �` | 1覐̏Փ� �y���L�V�R�̃��J�^���������z ��L�ӏ��ŁA���a��P�W�O�q�̃N���[�^�[�̍��Ղ��P�X�X�O�N��ɂ݂��� ���a10�`15�q�̏��f�����Փ˂����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��� 2.�ΎR�����̌��� 3.�a�C�i�`���a�j �u覐ΏՓˈȑO���狰���ނ̎�Ƃ��Ă̐�ł��n�܂��Ă���\��������v �u覐ΏՓˌ�����Ȃ�̊��ԁA�����͐������тĂ����\��������v �u��ł�Ƃꂽ������i�M���ށA���ށA��ށA�����ނȂǁj������̂͂Ȃ����v �Ƃ��������Ƃ��� �����ނ̐�Ŏ��̂�覐ΏՓ˂������Ƃ͌������A�Ȃ�炩�̕a�C�i�`���a�̖�������֔���Ƃ����̂�����j�������Ő�ł����Ƃ������i�؋��͂Ȃ��炵���j������ �@ |
|||||||
| �� | 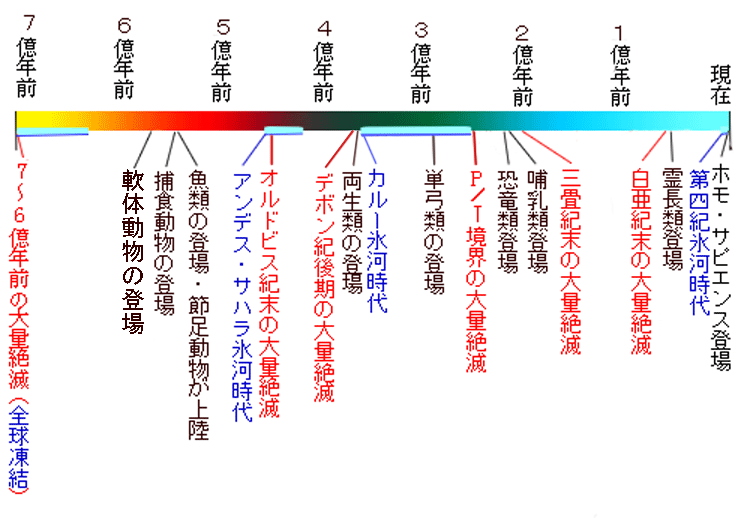 �@ |
�� | |||||||
| �@ | �@ | ||||||||
| �����̑�ʐ�� �����N���O�ɋN���������Ƃ��A�l�ނ��܂����܂�Ă��Ȃ�����̂��Ƃ��A�l�Êw�A�n���w�̋Z�ʂ������Ė��炩�ɂ����B ����́A�u�����ł���\���������v�Ƃ������_�ł���A��ɐ������Ƃ͌�����Ȃ��B �������A���炩�̏؋����琶�ݏo���ꂽ���̗��_�͓����Ȃ��ɂ͔ے�ł��Ȃ����̂ł�����B ������ʐ�ł̊Ԋu���݂Ă݂�� 1��9190���N�@�i�n�܂�`�n�܂�̊Ԃ́@2��7690���j 5700���N�@�i�n�܂�`�n�܂�̊Ԃ́@6910���N�j 1��4900���N 2500���N 1��3450���N �ƂȂ��Ă���B �܂���������Ă��Ȃ��u������ʐ�Łv�����邩������Ȃ��i�l�I�ɂ́A�m���ɂ����Ȃ����Ǝv���Ă���j���A �Œ���1��91900���N�A�ŒZ��2500���N�̊Ԋu�Ő����͑��ł��Ă���B ���݂����ԋ߂����ł��N�����Ƃ���Ă���̂��A6550���N�O�B �����̑�ʐ�ł��N�����������́A�����݂ŕ������Ă���ߋ��̎�����݂�ƃo���o���Ȃ̂ŁA�����Ƃ������̂͂���悤�ɂ͎v���Ȃ��B�Ȃ̂ŁA�u���N���ƂɁ`�v�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��������B �������A�ߋ��̍ŒZ�̊Ԋu�ł���2500���N�͂Ƃ����ɒʂ�z���Ă���̂ŁA���܂���ʐ�ł��N���Ă��s�v�c�͂Ȃ��Ƃ͌�����̂����B ������������A����͂����n�܂��Ă���̂�������Ȃ��B�C���t���Ă��Ȃ������ŁE�E�E�B �ƁA�|�����Ƃ������Ă݂͂����A �Œ��̊Ԋu�ł�2���N���炢����̂�����A�B�ς�������Ă������̂�������Ȃ��B ����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂�����\���͂��Ă��܂����ȁB �܁A���ʂƂ��ɂ͎��ʂ�B�N�ł��A�ǂ�Ȑ����ł��B �����̑�ʐ�ł̌����̂ق��ɂ̓p�^�[���͂Ȃ��̂��H �ƌ����A ���肻���ȋC�͂���B ���������́A 覐ΏՓˁ`�ΎR���������`�n���̊��≻ �̃p�^�[���� ���ƁA�V�~�����[�V�������Ă݂� 1.覐��Փ� 2.���������n��ɂ��鐶���͎��� 3.�Փ˂���覐ƏՓ˂����ꏊ�̕����i�{�Ռ��g�j�͍L�͈͂ɔ�юU��i覐�����ł������قǕ��ʂƔ͈͂͑傫���Ȃ�j 4.覐��������ꏊ�ɋ߂���߂��قǔ��ł��镨�̂�Ռ��g�̉e������ 5.覐��������ꏊ�̋߂��ɊC��傫�Ȍ�����A�Ôg���N���芪�����܂ꂽ�����͎��� 6.覐ΏՓ˂Ŋ����オ������ʂ̕��o�ɂ�葾�z�����Ւf����n�����≻���n�܂� 7.�i覐Ƃ����n���}�[�ʼn���ꂽ�j�n���̓}�O�}���������������� 8.�ΎR�����ɂ�镬���Ȃǂő��z���̎Ւf�������Ȃ�n�����≻�������� 9.�n�����≻�ɂ��C�ʒቺ���N���� 10.�n�����≻�����܂�ƂƂ��ɊC�ʏ㏸���n�܂�A���ω��ɑΉ��ł��Ȃ��������������� �Ƃ��������H ��������ł��������I���̑�ʐ�ł������N�������Ƃ����覐̑傫����10,000m�`15,000���i10�q�`15�q�j�ŁA�Փ˃G�l���M�[�͍L���ɗ��Ƃ��ꂽ����10�������������B ���Ȃ݂ɁA �n���ɂ͑�C�o���A�����邩��A������覐͑�C���C�Œn�\�ɓ�������O�ɏ��ł��邩�A�傫�����Ռ������Ȃ����Ă��܂��B ���Ă��A �u5m���炢��覐ł��P�s�s����ł�����З͂�����v�Ƃ������Ă���B 覐̑傫���Ɨ�����ꏊ�ɂ���Ĕ�Q�͂��Ȃ�ς���Ă����ł��傤�ȁB 10�q�قǂ�覐��Փ˂��Ċ��≻�ɂȂ����āE�E�E ��H �ł��A �uP�^T���E�̑��Łv�Ɓu�O��I���̑��Łv�̌�ɂ͕X�͎��オ�K��Ă��Ȃ� �����̑�ʐ�ł������N�����قǂ̑傫����覐�����������ƌ����ĕK��������K�͂Ȋ��≻�͋N���Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��H ���Ƃ���A �����̐�������S��ɋy�ԑ�ʐ�ł̌����́u覐̏Փˁv�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B �O��I���̑�ʐ�Ō�̕X�͎��オ��������Ă��Ȃ������H �����I���̑�ʐ�ŁA�������͑�l�I�X�͎���̔N��ݒ�ɊԈႢ������H �����̑�ʐ�ł̈������Ƃ��āu覐̏Փˁv���W�����܂�Ȃ��̂Ȃ�A ���炩�̌����ʼnΎR�����̌������N���� ��L�̃V�~�����[�V������7�`10�ɂȂ��Ă��� �Ƃ������Ƃ��낤 ���̌����� �E���f�������̉e���i��͓��m���Ԃ���Ƃ������Ƃ����邻�������j �E���̎���ɔɉh���Ă��鐶���̉e�� �Ȃ̂��낤�� ���������ɂ��Ă� �n���̑�C�̕ω��i�������ʂɂ���C�̑啝�Ȋ��g�ڍs�j���N����� �����̑�ʐ�łɂȂ��� �n���̗��j�͂�����J��Ԃ��Ă��� ����͓�����Ȃ� �������A �\������ƁA��ʐ�ł̌�ɂ͂Ȃ�炩�̊�Ղ��N���Ă���B �f�{���I����̑�ʐ�ł̌�ɂ́A�����ނ����܂� P�^T���E�̑�ʐ�ł̌�ɂ́A������M���ނ����܂� �O��I���̑�ʐ�ł̌�ɂ́A�����̑�ɉh���N�� �����I�̑�ʐ�ł̌�ɂ́A�쒷�ނ����܂�Ă���B ������������ �����̐i���ɂ́A��ʐ�łƂ����������K�v�Ȃ̂�������Ȃ� |
|||||||||
| �@ | 2020�N2��5���L�@ | �@ | |||||||
�Q�l���� �E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�t���[�S�Ȏ��T �@ |
|||||||||
�q�q�@���jTop �@ |
|||||||||
| Copyright (C) 2003�` ���i�R�� All Rights Reserved | |||||||||
�@ |
|||||||||
![[���i���i�Ɋւ��܂��ẮA�����N���쐬���ꂽ���_�ƌ����_�ŏ�ύX����Ă���ꍇ���������܂��B] [���i���i�Ɋւ��܂��ẮA�����N���쐬���ꂽ���_�ƌ����_�ŏ�ύX����Ă���ꍇ���������܂��B]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b286f6b.ce07e074.0b286f6e.ffa6a4a9/?me_id=1213310&item_id=18276436&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2203%2F9784569832203.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2203%2F9784569832203.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
