| 歴史 | ||||||||
感染症について / Infectious disease |
||||||||
| ■ | 感染症とは、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、異常プリオンによる病原体の感染によって宿主に異常が生じる病気の総称である。 ペニシリン(抗生物質)が発見されるまで対抗策はなかった。 |
■ | ||||||
ペニシリン 1928年にイギリスのアレクサンダー・フレミング博士が発見。 〜ブドウ球菌培養中にカビの胞子がペトリ皿に落ちて、そのカビの周辺のブドウ球菌が溶解していることに気付く〜 1929年、アオカビを液体培地に培養。その培養液を濾過した液体の中に抗菌物質が含まれていることを確認。この抗菌物質をペニシリンと名付ける。 1940年、発表。 1942年、ベンジルペニシリンが単離されて実用化。第二次世界大戦においての負傷者の多くを感染症から救った。 1945年、アレクサンダー・フレミング博士がノーベル生理学・医学賞を受賞。 その後、様々な抗菌剤が開発されることになるが、ペニシリンの発見がその源である。 |
||||||||
ウイルス感染について |
||||||||
| ■ | コロナウイルス禍で世界は大変なことになっている。 医療や福祉の業界に携わっている方々なら、感染症に対する知識を持っているとは思うが、感染症に向き合わなければならいケースを体験していない人は、その対応・対策の術を知る由もない。 感染症と言えば、これまでは「インフルエンザ」「ノロ」が主流で、毎年、乾燥時期になると、医療・福祉の現場では、ウイルスを持ちこまないように気を配ってきた。 それは、ほとんどのウイルスが高湿度と紫外線、高温に弱い性質を持っているからで、乾燥時期(冬季)はそれら(湿度、紫外線、気温)が低下するからである。 ・インフルエンザ・ウイルス 気温20℃以上、湿度50%以上で急速に死滅。 エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、紫外線に弱いとされる。 ・ノロ・ウイルス 75℃以上で1分間以上加熱(食品内部に入り込んでいる場合は4〜5分)などの高温殺菌で死滅。 次亜塩素酸ナトリウムに弱いとされている。 (要注意=ウイルスは多数の型があり、なおかつ進化もする。よって、すべてに同じ対応策で効果があるとは言えない) ウイルスは、細胞内に侵入しない限り増殖しない。 空気中に浮遊、または物体に付着したウイルスは、その種類、その場所の環境によって差異はあるが、一定の時間・期間で死滅(もしくは活動を停止)する。 乾燥時期に流行する原因として、乾燥時期は湿度が下がり、空気中にウイルスが浮遊しやすくなるため。 湿度が高いと、ウイルス(または埃)に湿気がまとわりついて落とす効果があり、ウイルスを体内に取り込む可能性が低くなるからである。 ウイルスは目に見えないので、どこで感染してしまうのかはわからない。 言えるのは、ウイルスを体内に入れさえしなければ感染しないということだ。 ウイルスが体内に入り込む場所は、口、鼻、(目、排泄器官、傷口)だ。 ・口 唾液を飲み込んだり、飲食物を体内に取り込んだりする場所で、口を開けることによって外気にさらされる。最も、ウイルスが侵入しやすい経路といえる。 ウイルスが付着しているものを口の中に入れる。浮遊しているウイルスを吸い込んでしまう。 ・鼻 普段から外気にさらされている場所なので、吸い込む(すする)ことによってウイルスの侵入を許してしまう。 ・目、排泄器官 物を取り込む器官ではないが、体内へ通じている場所であり、傷つきやすい部分なのでウイルスが侵入する可能性がある。 ・傷口 傷口にウイルスが付着し、血管を通じて体内へと運ばれてしまう。 病原体が口、鼻、目、排泄器官、傷口から侵入したからと言って、即感染(発症)となるわけではない。 病原体の種類によっては、血液中に入り込んでもそこで死滅するものもあれば、B型肝炎などのように血液・体液を主なルートとするものもある。 空気感染・・・はしか、水ぼうそう、結核など 飛沫感染・・・インフルエンザ、風疹、おたふくかぜなど 接触感染・・・インフルエンザなど 経口感染・・・ノロなど 粘膜感染・・・エイズ、B型肝炎など 傷の無い皮膚からは、ウイルスは直接侵入できない。 よって、怪我をしていない手からもウイルスは体内へ侵入できない。 なのに、 なぜ予防策として手洗いが重要なのか? 人間の体の中で、一番いろんな場所に触れるのが手だ。 いろんな場所を触るということは、ウイルスに触れる可能性も一番高い。 ウイルスの侵入経路に一番触れるのも手である。 人は、無意識のうちに口や鼻の周りやそのものに手を持って行ってしまう。自撮り動画をしてまでチェックする必要はないが、思った以上に、無意識のうちに、頻繁に手で顔(特に口と鼻)を触っているということは覚えておいたほうが良い。 だから、手洗いは大事! 周りに感染者がいなくても、ウイルス予防する必要があるの? ウイルスは目に見えないので、予防しておいて損はない。 ◎外出先 ○近くに人がいない場所 マスク(フェイスガードや防護眼鏡なども)の必要なし ○近くに人がいる場所 マスク(場合によっては、フェイスガードや防護眼鏡も)は必要。 外出時に誰かが触れるような場所(ドアノブ、手すり、ボタン、テーブルなど)を触った後で、手洗い・消毒は必要。 ◎外出から(自宅や職場などに)戻ったら ・室内のものに触る前に、できるだけ早く手洗い・消毒を行う。 ・自宅に戻った場合で、時間に余裕があるのなら、お風呂で全身を洗って着替えもすれば完璧。 着替えた衣類はすぐに洗濯する。 手洗いはしないよりもしたほうがいい。 水で洗うよりも温水のほうがいい。 石鹸を使わないよりは使ったほうがいい。 石鹸を使った手洗いもしっかりした洗い方のほうがいい。 手洗いした後で消毒もしたほうがいい。 手洗いの仕方 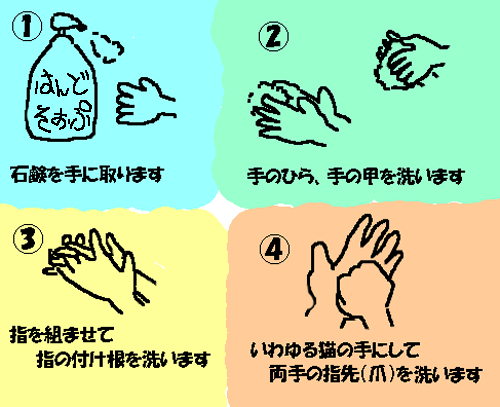 露出していたのであれば、二の腕まで洗ったほうがいい。 手首までは洗うようにしましょう。 感染していない人が個室にこもっている分には、ウイルスに侵されることはない。 ただし、外界と行き来している人と同じ空間を共有しているなら話は別。その人を介して感染する可能性はある。 また、宅配、宅急便、訪問販売、押し売り、勧誘、集金、強盗など、外から来た人と接触した時にも感染する危険性はある。 この時も、手洗い、消毒、うがいはしておいて損はない。 コロナ・ウイルスのように発症してなくても、周りにウイルスをばらまいてしまうタイプもある。発症していないから保菌している側も自覚がない。油断を招いてしまう厄介なタイプだ。 同じ空間を共有している人が保菌しているかどうかがわからないので、室内でも注意が必要といえる。 室内でもマスクは必要? マスクの効果はこのように言われている。 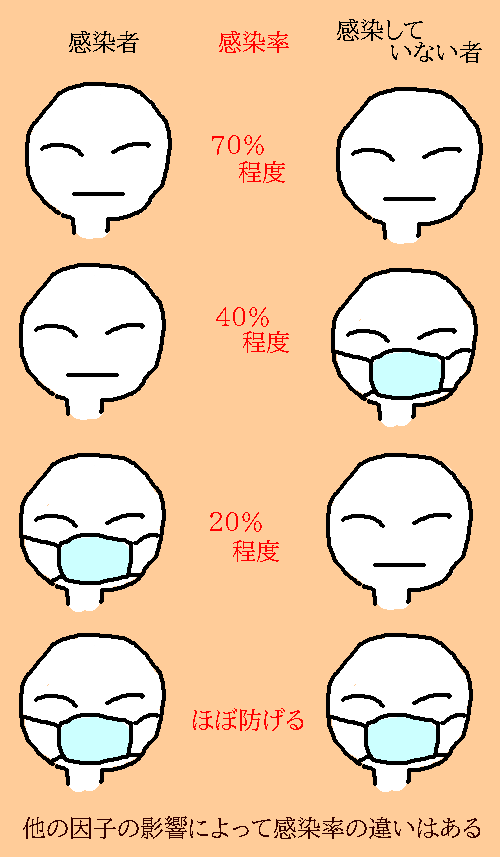 マスクをするしないで感染率は大きく変わってくる。 というのがよくわかる。 次に、マスクの種類についてだが、 ○ガーゼ・・・ガーゼを折り重ねたもの。折り重ねる回数が多いほど粒子の遮断が見込める。 ○不織布・・・繊維を織り込まない形で布にしたもの。加工の仕方により遮断効果に違いが出る。 ○サージカル・・・装着した人から排出される粒子(微生物)が大気中に拡がるのを抑えるためのもの。 ○N95・・・装着した人を外気(に含まれた粒子・微生物)から守るために作られたもの。装着時に隙間ができにくい形状になっている。 ○防護(防毒)・・・形は様々で、大きいフィルターを装備し生物化学兵器を完全に遮断する目的で作られたもの。 などがある。 一概に、厚い、大きいからといって効果が大きいとは限らない。 BFE・・・細菌濾過効率 PFE・・・微粒子濾過効率 で何%か書かれていれば、それを目安にできる。 使い捨てマスクに多く見られるブリーツ型や立体型のものは、その素材や加工の仕方によって効果が変わってくる。 やはり、効果が大きいものは装着時に息苦しさはついて回る。 呼吸しやすい、装着感が薄いといったものは、相当の技術・素材を使ったものでない限りは効果は期待できないだろう。 ただ、どんなマスクであろうと「着けないよりは着けたほうがいい」。菌が付着しているマスクでない限り。 装着時はきちんとした着け方をしないと、そのマスクの持つ効果を発揮させることができない。 鼻を出した状態の、いわゆる口マスクの人をたまに見かけるが、何も着けていないよりはいいのだろうが、そんなんだったらマスクをつける意味がないと私は思う。 「マスクをすると息苦しいのよね」「マスクをすると気持ち悪くなる」 などと、マスクが不得手な人がたまにいる。私はマスクに抵抗がないので、そういう方々の気持ちがよくわからないのだが、自分や目の前にいる人たちを守るためだと思って我慢してください。としか言いようがない。 ◎敷地内でのマスクの着用 ○自宅 全くの他人に比べると、家族のほうが生活行動はある程度把握しやすい。(のではないかなぁ・・・) そういった意味から、家族が外からウイルスを持ち帰って来る可能性がどの程度のものか想像することはできると思う。(たぶん) なので、自宅でまでマスクをして生活する必要はないであろう。 放蕩的な生活行動の家族がいる場合は、防護が必要だろうけど。 ○職場や不特定多数の人が集まる場所 自分の近くにいる人がどんな行動をしているのかを把握するのは難しい。 歓楽街で遊び歩いている人なのかもしれないし、体調を崩しているのを隠して出歩いている人なのかもしれない。 感染者(保菌者)である可能性は高まるばかりである。 したがって、そういう場所でのマスクの着用は必須といえるだろう。 ◎感染者(発症者) 感染者(発症者)は、マスク着用、こまめな手洗い・うがいをするようにし、体調を崩さないように気を付けた生活をするよう心掛ける。症状が治まり、ウイルスが完全に死滅する迄の期間は隔離となる。 ウイルスに感染したと思われた場合は、速やかに医療機関、保健所などの専門機関に連絡・相談をして、その指示に従うのがよい。 ワクチンがあるウイルスであれば、それを投与することになるだろうし、ウイルスの種類によって隔離の期間は異なるので医者・専門家の指導に従うことが大事である。 ◎感染者に関わる側 感染者に何らかのかかわりを持つ場合は、完全防護であたらなければならない。 感染者が隔離されている室内は、ウイルスがあちこちにいるものと思ったほうが良い。 ヘアキャップ、防護眼鏡(フェイスシールド)、マスク、手袋、防護服(コート、エプロン)、靴カバーなどを装備して、全身を守らなければならない。 ウイルスの種類によって異なるが、アルコール、次亜塩素酸などの消毒液も用意しなければならない。 ◎隔離された感染者に対応する場合 隔離部屋の入り口に、そのウイルスに適した消毒液のスプレー、消毒液をしみこませたマット、ゴミ袋、蓋つきのバケツ(または蓋つきのゴミ箱)などを用意しておく。 防護用具を着けたら、その上から消毒液を全身スプレーする。靴底も消毒液をしみこませたマットの上で数回足踏みをすることで消毒する。(マットを用意できない場合は、消毒スプレーを吹き付けてもよい) 〜この時点で全身がほぼ防菌コーティング状態〜 (多少のウイルスは付着したとたん死滅へと向かう) 隔離部屋へ入室したら、感染者との不必要な接触はなるべくされて行動する。用件が済んだら速やかに退室する。 問題は隔離部屋から出てから(出方)だ。 いくら(ほぼ)防菌コーティングしたとはいえ、完全ではない。 防護用具に付着したウイルスを除去しなければならない。隔離部屋からウイルスを外に出してしまっては、隔離した意味がなくなってしまう。 まず、防護用具の上から消毒液で全身スプレーする。 ゴミ袋と蓋つきのバケツ(蓋つきのごみ箱)の内側にも消毒液をスプレーする。(または流し込む) 隔離部屋から持ち出した物を、ゴミ袋、バケツ(ゴミ箱)に入れる。 捨てるものはゴミ袋へ、捨てずにまた使うものはバケツ(ゴミ箱)へ入れるようにする。 次に、外した防護用具をゴミ袋、またはバケツ(ゴミ箱)に入れていくのだが、 ヘアキャップ コート(エプロン) 靴カバー の順で裏返しながら脱いで、ゴミ袋、バケツ(ゴミ箱)に入れる。 ここで、マスクや眼鏡(フェイスシールド)も外したほうが良いのでは?と思いがちだが、ウイルスが一番付着している可能性が高い手袋は、なるべき顔に近づけないほうがいいので、 次に手袋を、素手で表側をなるべく触らないようにしつつ裏返して外す。 消毒スプレーを空中散布。 消毒液の染みたマットで足踏み。(またはスプレー) そして、手洗いができる場所に移動して、眼鏡(フェイスシールド)、マスクを外す。 手洗い・うがい(洗顔)し、新しいマスクを装着。 洗顔については、防護用具を装着していても頬など顔の一部が露出してしまうので、その部分に付着したウイルスを除去する目的がある。 感染者が周囲にいない状態なら、感染症対策はいらない。 しかし、ウイルスを撲滅できていない状態なら、まったく無防備ではいられない。 どこかで、自覚のない(もしくは感染予防についての知識のない)感染者(保菌者)と出会ってしまうかもしれないからだ。 行動範囲が広ければ広いほど、その確率は上がる。 怖いですね〜。 自分だけは大丈夫 この発想が最も危険だと言える。 本物の超人・スーパーマンであれば大丈夫なのだろうが、残念ながら現実世界ではそんなものは存在しない。 自分が発症しなかったり、重症にならなかったりしたとしても、ウイルスをばら撒かないとは限らない。あなたが保菌してしまったウイルスに感染した人が重症化・死亡してしまうかもしれない。 あなたの軽率な行動が、誰かを苦しめたり、誰かを悲しませたり、誰かを殺したり、ウイルス撲滅の日を先送りにしたり、人類滅亡を招くかもしれない。 過度な防衛行動もどうかと思うが、あまりにも能天気な行動は危険である。 ウイルスに感染したら、額にマークが出るとか、頭上にマークが浮かぶとか、そういう分かりやすいのがあればいいのにね。 残念ながら、今のところ、現実世界にそんな便利なシステムはないので、個人個人で気を付けて生活していきましょう。 |
■ | ||||||
コロナ禍で世界が大変である。 そんな中で、みなさんソーシャル・ディスタンスを守るよう心掛けて生活しております。 テレビ各局も番組内で出演者の距離を離したり、リモート映像出演などで対応したりしております。 そんな中、とある番組で「ん?」と感じたことがありました。 その番組は料理番組でした。 キッチンテーブルに二人の出演者。 2mほど離れて、ソーシャル・ディスタンスを守っての立ち位置。 物を渡したりする際にも、道具を使って二人の距離が縮まない工夫がされておりました。 ソーシャル・ディスタンスを保っているので、出演者のどちらかが感染(保菌)していたとしても、多少は相手に感染させてしまう確率は低くなっているといえるでしょう。 しかし、いかんせん料理番組。 調理をするんですな。これが。 テレビ番組なので、調理をしながらしゃべらなければいけません。 盛り付け時もしゃべりまくります。 でも、出演者の二人はマスクもフェイスシールドも着用しておりません。 間違いなく、唾が料理に降り注いでおります。 大丈夫でしょうか? もし、 「出演者は(撮影前に何らかの検査を受けて)感染(保菌)していないことを確認しております」 というのなら、出演者がソーシャル・ディスタンスをとる必要はありません。 もし、 「番組最後に食べているものと、番組中に作っていたものは別物で、出演者の唾が降り注いだ可能性のあるものは破棄しております」 とか 「調理時に5分以上加熱しておりますので、ウイルスは熱殺菌されていると判断しております」 だったら、何の文句もありませんけど。 (ただ、新型コロナが熱殺菌できるかどうかで文句の言いようも出てきますけど) そもそも、 テレビ番組でソーシャル・ディスタンスをとるようになったのを見たときに 「どうせ、打ち合わせとか、カメラが回ってないときは普通に接して話してるんでしょ」 と思ったものだ。(違ったらごめんなさいだけど) な〜んか、建前だけというか、見てくれだけで中身がないというか。 所詮は虚栄・虚像・虚無の世界なんだからしょうがないんでしょうけど。 と、いちゃもんを付けては見たものも テレビ局での集団感染という報告がない(あったとしても少ない)ということは、予防対策がなされている(またはたまたま運よく感染者がいない)ということなんでしょうな。 |
||||||||
| 2020年7月記 | ||||||||
参考資料 ウィキペディア(Wikipedia)フリー百科事典 |
||||||||
〈〈 歴史Top |
||||||||
| Copyright (C) 2003〜 黒麒燃魂 All Rights Reserved | ||||||||