| ���j | ||||||||||||||||
�X�͎���@/�@�X�͊��@/�@�X���@/�@�ԕX�� �@ |
||||||||||||||||
| �@ | �@ | |||||||||||||||
| �n��46���N�̗��j�̒��� �����̑�ʐ�łƂ������̂��Œ�ł��v6��N�����Ă��� ���̃y�[�W�̕\�ɔ��g�ŕX�͎���ƕX�����L���Ă��邪 ���������N���Ă��� ���Ƃ����̂� �������Ă������� �撣���Đ������тĂ��� �X�͎���i�X�����j �n����ɑ嗤���݂̑傫���̕X�������鎞���X�͎���Ƃ��� �X�����Ƃ������炵�� �X�͎���Ƃ����� �n����ǂ������������^���� �Ǝv���������� ����͊ԈႢ �ǂ������������^�����������ɂȂ����ł��낤�X�͎���i�X�͊��j��1�x���� 7��2�疜�N�O�`6��3��5�S���N�O�i��������8��5�疜�N�O�`6��3�疜�N�O�j �ɋN�����S������ �N���C�I�W�F�j�A���X�͎���̂� ���̕X�͎���� ���Ɖ��g�Ȓn������������ۂ� �Ȃ��Ȃ� ������X�͎��ゾ���� ���݁A�t�ďH�͐Ⴊ�����n�悪�����ł���� �Ă͓��ɏ������炢�ł���� �ł��X�͎���Ȃ�ł� �X�͎���̒�`�� �n����ɑ嗤���݂̑傫���̕X�������鎞�� ������ ���� �k�ɂƓ�ɂɈ�N���傫�ȕX��������܂���� �Ƃ������Ƃ́A ���� �����݁A��l�I�X�͎���^���Œ��Ȃ�ł� �������A �i���������ފ��Ƃ��Ắj���g�Ȓn�悪���� �Ȃ̂ŁA ���̕X�͎��������Ȋ�����������Ȃ����� �Ƃ������ƂȂ̂ł� �����āA �t���l����� �X�͎���ȊO�� �S�嗤�ɕX�������������Ƃ������ƂȂ̂ł� ��ɂɂ��k�ɂɂ��X�������� �C�ʂ����������ł��傤�� ���ϋC�������������ł��傤�� �悭����Ȋ��Ő����͐i�����Ă��������̂ł� �X�� �X�͎���̒��� �C���̒ቺ���Ԋu��u���ĖK��� �C�����ቺ����ƕX�͂����B���� ���������������̂��Ƃ�X���Ƃ��� �X���ƕX���̊Ԃ̋C������r�I�ɂ₩�Ȏ������ԕX���Ƃ��� ���݂͊ԕX�� 1���N�O���炢����ԕX���ɓ������炵���ł� �X�͊� �� �X�͎���ƕX�����čl�����Ă��Ȃ���������ɂ� ������S�Ă�X�͊� �ƕ\�����Ă��� �X�͊��i���ł����X�͎���j���ɂ����g�̎��������邱�Ƃ������ �����X���A�ԕX���ƕ\�����邱�ƂɂȂ��� �傫�Ȋ���ł̊�����͕X�͎���Ƃ� �X�͊��Ƃ����P��͕X���Ɠ��`�Ƃ��܂��傤 �ł��A���������Ⴂ����������X�͊��Ƃ����P��͂Ȃ�ׂ��g��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�� �ƁA���{��X�w������Ă���炵�� �ł� ���Ɛ��Ƃ̐l�ł��� �X�͊��Ƃ����P����g���ĕ\�����Ă��� �X�͎���i�X�����j���X�����������Ă��܂��Ă���̂��݂����܂� �ԈႢ�₷���̂� ���ӂ��܂��傤 |
||||||||||||||||
| �@ | �@ | |||||||||||||||
�n���a���`�����a���`���݂܂ł̔N�\ 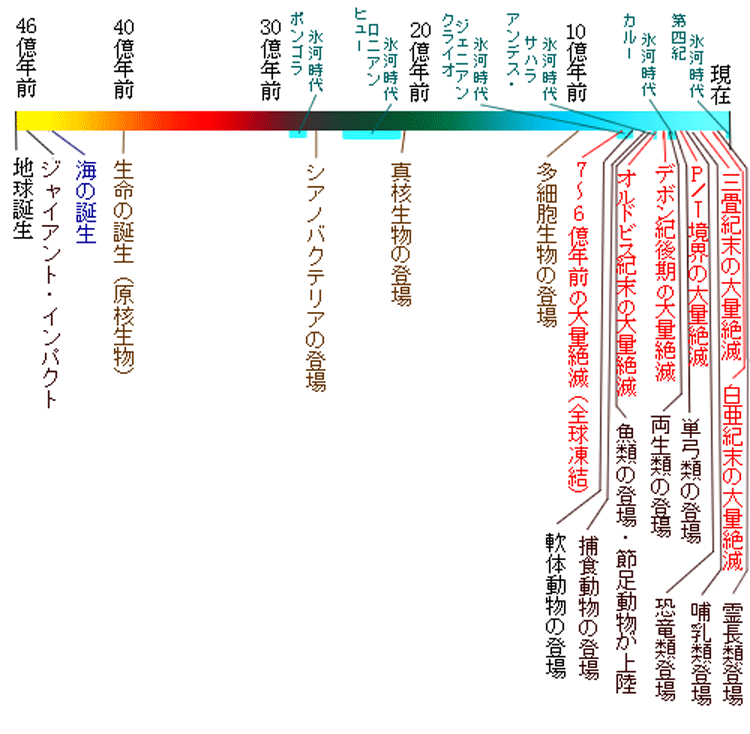 �@ |
||||||||||||||||
7���N�O�`���݂܂ł̔N�\ 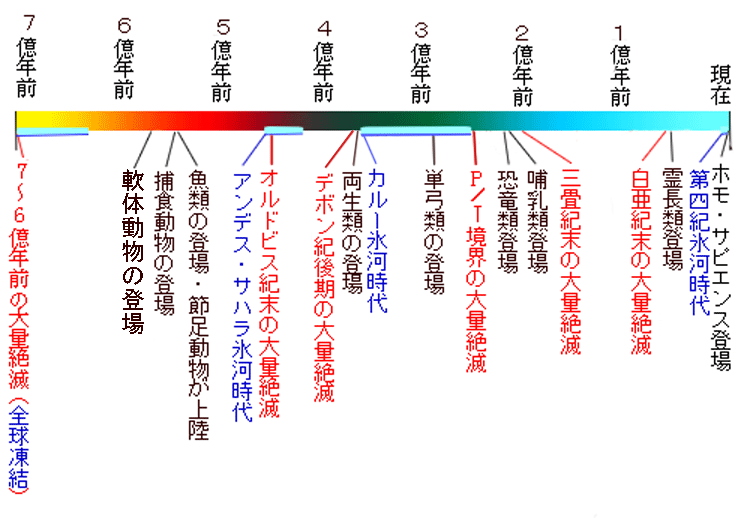 �@ |
||||||||||||||||
�k�����l�`���݂܂ł̔N�\�i���l�a���`�����l�ޓo��܂ł̔N�\-�ʐ}�j 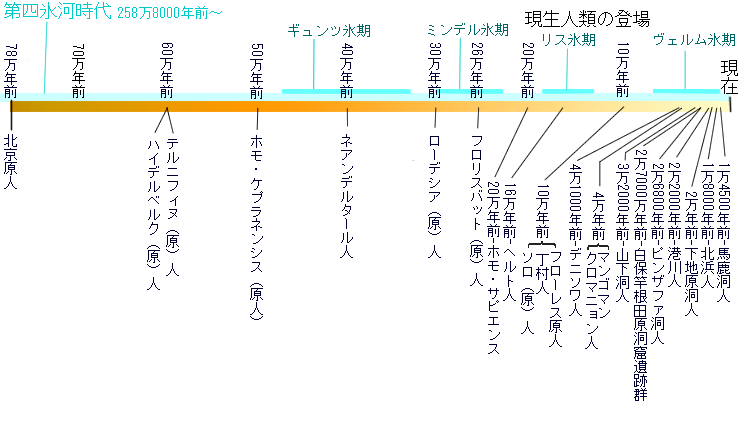 �@ |
||||||||||||||||
�n���a�����猻��܂ł̗��N�\ �@ |
||||||||||||||||
�� �� �� �@ |
�� �J �� �u �� �A �� �� �@ |
�� | 4,600,000,000�N�O �i46���N�O�j �@ |
�� | �n���a�� | �� | ||||||||||
�� �� �� �@ |
4,000,000,000�N�O�` 3,800,000,000�N�O �i40���`38���N�O�j �@ |
�n�����a�����Ă���6�`8���N�قnjo���������������a�� ���j�����ƌĂ���ۗނȂ��̐��������̐����ł��� 2016�N9�� �O���[�������h��37�`38���N�O�̂��̂Ƃ݂���X�g���}�g���C�g�i�����ނƑ͐ϕ������w�ɂ��ςݏd�Ȃ��Ă��鉻�j����������Ă��� �@ |
||||||||||||||
2,900,000,000�N�O�` 27,800,000,000�N�O �i29���N�O�` �@27��8000���N�O�j �@ |
�@�|���S���X�͎��� �@ |
|||||||||||||||
2,700,000,000�N�O �i27���N�O�j �@ |
����̌`�� �������a�����Ă���13���N�قnjo���� �V�A�m�o�N�e���A�i�����ށj���o�� �@ |
|||||||||||||||
�� �� �� �@ |
2,500,000,000�N�O �i25���N�O�j �@ |
|||||||||||||||
2,450,000,000�N�O�` 2,100,000,000�N�O �i24��5000�N�O�` �@21���N�O�j �@ |
�@�q���[���j�A���X�͎��� �@ |
|||||||||||||||
2,100,000,000�N�O �i21���N�O�j �@ |
�V�A�m�o�N�e���A�o�ꂵ�Ă���6���N�قnjo���� �~�g�R���h���A�A�t�Α̂Ȃǂ���荞���^�j�����o�� �A���זE�A�����זE�ւƐi�����Ă��� �@ |
|||||||||||||||
720,000,000�N�O�` 635,000,000�N�O �i7��2000���N�O�` �@6��3500���N�O�j �@ |
|
|||||||||||||||
570,000,000�N�O �i5��7000���N�O�j �@ |
�G�f�B�A�J�������Q �k�⍜�������Ȃ���̐��̊C�m�����Ǝv����u�f�B�b�L���\�j�A�v�u�`�����j�I�f�B�X�N�X�v�u�L���x���v������������Ă��� �@ |
|||||||||||||||
�� �� �� �@ |
�� �J �� �u �� �A �I �@ |
�J �� �u �� �A �I |
542,000,000�N�O �i5��4200���N�O�j �@ |
�Z���Ԃ̂����� �ߐH�����i�ߑ������j�o�� �����͖ڂ�G��A���Ȃǂ���ɓ���� �A�m�}�J���X�F�k�A�����J�A�����A�I�[�X�g�����A�Ŕ��� �O�t���F�k�A�����J���Ŕ��� �I�p�r�j�A�F�J�i�_�Ŕ��� �Ғœ����i���ށj���o�� �@ |
||||||||||||
�� �� �� �@ |
541,000,000�N�O �i5��4100���N�O�j �@ |
|||||||||||||||
�I �� �h �r �X �I �@ |
488,300,000�N�O �i4��8830���N�O�j �@ |
�����̒��ɗ������̂������ �@ |
||||||||||||||
450,000,000�N�O�` 420,000,000�N�O �i4��5�疜�N�O�` �@4��2�疜�N�O�j �@ |
�@�A���f�X�[�T�n���X�͎��� �@�i4��6�疜�N�O�`4��2�疜�N�O�@�Ƃ����������j �@ |
|||||||||||||||
444,000,000�N�O �i4��4400���N�O�j �@ |
�I���h�r�X�I���̐�����ʐ�� �������85������� �����Ƃ��āA���V�������̉e�����A�ΎR���ɂ�銦�≻�������� �@ |
|||||||||||||||
�V �� �� �I �@ |
443,700,000�N�O �i4��4370���N�O�j �@ |
�I���h�r�X�I���̐�����ʐ�ł����т������̒��������Ƀg�Q���������i�����ށj������� �@ |
�@ | |||||||||||||
�f �{ �� �I �@ |
416,000,000�N�O �i4��1600���N�O�j �@ |
���҂ƂȂ������ނɒǂ���悤�� �ߑ������̒����痤�֏オ�鐶�����o�� �@�@ |
||||||||||||||
374,000,000�N�O �i3��7400���N�O�j �@ |
�f�{���I����̐�����ʐ�� �������82������� �����Ƃ��āA��C�ϓ��ɂ�銦�≻���A���V�̏Փː������� �x���M�[�y�ђ����암�̒n�w���珬�V�̏Փ˂̏؋�������Ă���炵�� �Ғœ����̒����痼���ނ��o�� �����i�C��͐�j���Z�݂ɂ����Ȃ����̂� �H���i�����Ȃǁj��ǂ������ĂȂ̂� �l���A�ċz�튯�A�����O��Ȃǂ�g�ɒ����ĐҒœ����̈ꕔ�͗��֏オ���� �@ |
|||||||||||||||
360,000,000�N�O�` 260,000,000�N�O �i3��6000���N�O�` �@2��6000���N�O�j �@ |
�@�J���\�X�͎��� �@ |
|||||||||||||||
�� �Y �I �@ |
359,200,000�N�O �i3��5920���N�O�j �@ |
�ΒY�I�ɐߑ������i�����j�͋��剻�𐋂� ���K�l�E���F�H���L�����傫�����V�O�p������g���{ ���I�f�B�N�e�B�I�v���F�H���L�����傫��40�����̃J�Q���E �A�[�X���v���E���F�F�̒��Q�`�Rm�̃��J�f�̂悤�Ȑ����� �p���I�e�[���F�̒��R�O�����̃N�� �}�m�u���b�^�F�H���L�����傫����11cm������S�L�u���̒��� �Ȃǂ����������� �@ |
||||||||||||||
�y �� �� �I �@ |
299,000,000�N�O �i2��9900���N�O�j �@ |
�p���Q�A���嗤���`�������� �������Ŋ��������n�܂� ����ɑΉ������Ғœ����̒�����P�|�ނ��o�� �f�B���g���h���F�k�A�����J�Ŕ��� ���̒P�|�ނ��M���ނq�����Ă������ƍl�����Ă��� �@ |
||||||||||||||
251,000,000�N�O �i2��5100���N�O�j �@ |
�M���ނ̎Y�������������̂悤�� �y���������i�o�^�s���E�j�̐�����ʐ�����N���� �@�o�^�s��Permian�i�y�����I�j-Triassic�i�O��I�j �X�O���̐��������ł��� �����Ƃ��āA�ΎR�����̌������A���≻�ɂ��C�ʌ�ނ��N���ĐH���A���̃o�����X���傫�����ꂽ���Ȃǂ����� �@ |
|||||||||||||||
| �� �� �� |
�O �� �I �@ |
250,000,000�N�O �i2��5000���N�O�j �@ |
||||||||||||||
200,000,000�N�O �i2���N�O�j �@ |
�O��I���̐�����ʐ�� �����Ƃ��āA�ΎR�����̌�������覐ΏՓː������� ��ԉe�������̂���ނŁA���̂قƂ�ǂ���ł����Ƃ����Ă��� 覐ΐ��̏؋��Ƃ��āA �y�J�i�_�A�P�x�b�N�B�̃}�j�N�A���K���E�N���[�^�A�}�j�g�o�B�̃Z�C���g�E�}�[�e�B���E�N���[�^�[�z �y�t�����X�A���V���V���[���E�N���[�^�[�z �y�E�N���C�i�A�I�{�����E�N���[�^�[�z �y�A�����J�A�m�[�X�E�_�R�^�B�̃��b�h�E�E�C���O�E�N���[�^�[�z ���������Ă���B �j�ӂ����V�́i���a3.3�`7.8�q���x�j���������ɗ����i�Փˁj�����Ƃ����B �@ |
|||||||||||||||
�W �� �� �I �@ |
199,600,000�N�O �i1��9960���N�O�j |
�W�����I��������������ނ̒����璹�ނւƐi��������̂������ �@ |
||||||||||||||
�� �� �I �@ |
145,500,000�N�O �i1��4550���N�O�j �@ |
|||||||||||||||
66,000,000�N�O���� �i6600���N�O����j �@ |
�����āA �����I���i�j�^�s���E�j�̋����S�� �����Ƃ��āA�ΎR������������覐ΏՓː��Ȃǂ����� �E1990�N�� �@���L�V�R�̃��J�^���������Œ��a��P�W�O�q�̃N���[�^�[�̍��Ղ��݂���A���a10�`15�q�̏��f�����Փ˂����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���i覐ΏՓː��j �@ |
|||||||||||||||
�V �� �� |
||||||||||||||||
�� �� �O �I �@ |
66,000,000�N�O �i6600���N�O�j �@ |
|||||||||||||||
�V �� �O �I �@ |
23,030,000�N�O �i2303���N�O�j �@ |
|||||||||||||||
�� �l �� �@ |
2,588,000�N�O�` �@���� �i258��8000�N�O�` �@���݁j �@ |
�@��l�I�X�͎���i�V����X�͎���j �@�i258���N�O�`���݁@�Ƃ����������j �@ |
||||||||||||||
2,500,000�N�O �i250���N�O�j �@ |
||||||||||||||||
470,000�N�O�` 330,000�N�O �i47���N�O�` �@33���N�O�j �@ |
�@�M�����c�X�� �@ |
|||||||||||||||
330,000�N�O �i33���N�O�j �@ |
�@ | |||||||||||||||
300,000�N�O�` 230,000�N�O �i30���N�O�` �@23���N�O�j �@ |
�@�~���f���X�� �@ |
|||||||||||||||
230,000�N�O �i23���N�O�j �@ |
�@ | |||||||||||||||
180,000�N�O�` 130,000�N�O �i18���N�O�` �@13���N�O�j �@ |
�@���X�X�� �@ |
|||||||||||||||
130,000�N�O �i13���N�O�j �@ |
�@ | |||||||||||||||
70,000�N�O�` 15,000�N�O �i7���N�O�` �@1��5000�N�O�j �@ |
�@���������X���i�ŏI�X���j �@�i�I����������1���N�O�O��Ƃ����������j �@ |
|||||||||||||||
15,000�N�O �i1��5000�N�O�j �@ |
||||||||||||||||
�@���� �@ |
||||||||||||||||
| �@ | �@ | |||||||||||||||
| �u�X�͎��オ����܂ő����Ă���v �ƕ����Ƃт����肳���������邩������Ȃ��B �u�X�͎���A�X�͊��v�Ƃ����P��̈�ۂ� �u�n���S�̂��^�~��ԁv �ƘA�z���Ă��܂�����ł��낤�B �u���Ă������̒����}�����X�������Ă���v �Ƃ� �u��ɕ���ꂽ��n�̒��Ń}�����X�����є�𒅂����n�l�v �Ƃ������}���ߋ��ɂǂ����Ō������Ƃ̂���l�͏��X�ł���B �n����̂ǂ�������������ƕX�̐��E ���ꂪ�u�X�͎���A�X�͊��v �����v���Ă��܂��Ă�����͊��Ƒ����Ǝv���B �ł�����͊ԈႢ�ł���B ���X�͎���i�X�����j ���E�I�ɋC����ɂȂ�A�嗤���݂͈̔͂̕X�������݂��Ă��鎞�� �Ƃ������ƂȂ̂ŁA ����͓�ɂ�k�ɕt�߂ɍL��ȕX�������݂���̂ŕX�͎��ゾ�Ƃ�����B �n���S�̂��قڂقڐ��X�ɕ�܂�Ă��܂��̂� �u�X�m�[�{�[���A�[�X�v �Ƃ����B ���X�� �X�͎���̒��ŁA ���≻���g�債���ܓx�n��܂ŕX�͂�X���ɕ�����悤�Ȏ����������B ���ԕX�� �X�͎���̕X���̒��ŁA ��r�I���g�ɂȂ�X�́E�X�����k�����Ă��鎞���������B �Ȃ̂ŁA ����A�X�����K���A����͕X�͎���̊ԕX���ƂȂ�B ����A�X�����K��Ȃ���A�X�͎���̏I���ƂȂ�B ���X�͊� �X�͎���ƕX���̗������w�����t�Ƃ��Ďg���Ă������A �u���{��X�w��v�Ƃ����Ƃ���ł́A �u�i�X���Ɠ��`��Ƃ��������Łj����������邽�߁A ����́g�X�͊��h�̎g�p������g�X���h���g�p����ׂ��v �Ɩ������Ă���炵���B �Ƃ͌����Ă��A �u�X�͎���v�u�X���v�����u�X�͊��v�Ƃ����P��̂ق��� ��ʓI�ɂ̓��W���[�Ɏg���Ă���C������B ���ɕ��w��i�▟��E�A�j���Ȃǂł́u�X�͊��v�ƕ\�����Ă���P�[�X�������Ǝv���B ���ĂȊ����Łu�X�͎���v���l���Ă݂�ƁA �X�͎��ザ��Ȃ���������Ȃ�āA�{���ɂ���̂��낤���H �Ǝv���Ă��܂��B ��ɕt�߁A�k�ɕt�߂Ɋ��X��������ԁE�E�E ���낵���قǂ̉��g�i�Ƃ������ܔM�j��ԂȂ̂ł͂Ȃ����낤���H �܁A�����Ȃ邩�ǂ����́A���z����̊�������Ȃ낤���� �ɒn�ɕX���Ȃ��Ȃ�قǂ̔M�����B �����͂��̎ܔM�n���̒��� �i�Ƃ����Ă��A�C�������x�Ȃ̂��͌v��m��j �����ł���̂��낤���H |
||||||||||||||||
| �@ | 2020�N2��24���L�@ | �@ | ||||||||||||||
�Q�l���� �E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�t���[�S�Ȏ��T |
||||||||||||||||
�q�q�@���jTop �@ |
||||||||||||||||
| Copyright (C) 2003�` ���i�R�� All Rights Reserved | ||||||||||||||||
�@ |
||||||||||||||||
![[���i���i�Ɋւ��܂��ẮA�����N���쐬���ꂽ���_�ƌ����_�ŏ�ύX����Ă���ꍇ���������܂��B] [���i���i�Ɋւ��܂��ẮA�����N���쐬���ꂽ���_�ƌ����_�ŏ�ύX����Ă���ꍇ���������܂��B]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b286f6b.ce07e074.0b286f6e.ffa6a4a9/?me_id=1213310&item_id=18276436&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2203%2F9784569832203.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2203%2F9784569832203.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
