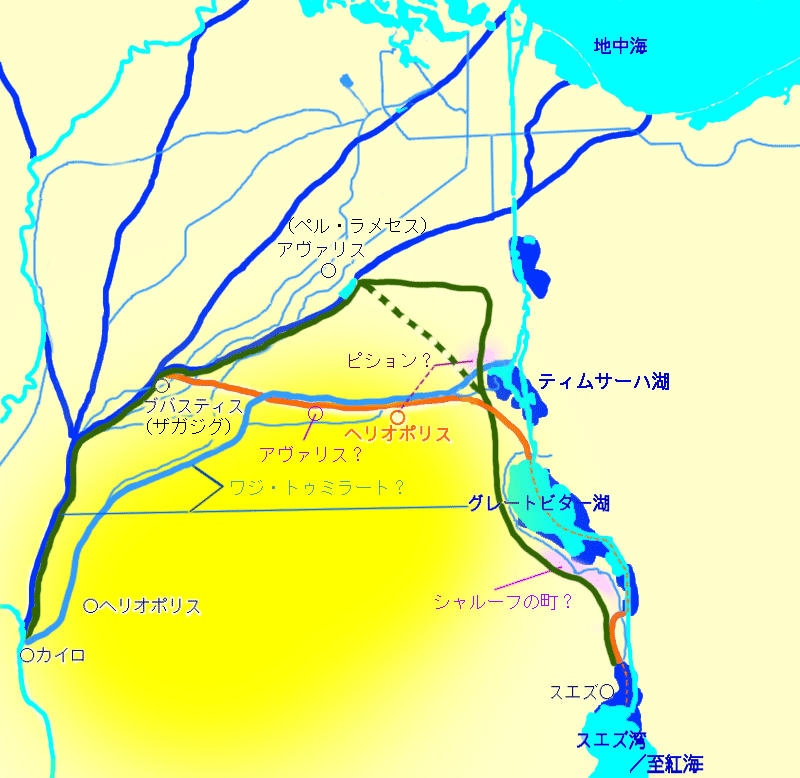| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリスト教 / Christianity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナザレのイエスをキリスト(救世主/救い主)、神の子とし、神(ヤハウェ/デウスなど)は唯一とする一神教の宗教。 世界の信者数は23億人以上と言われている。(2020年の時点で、世界の人口は77億人~78億人と言われている。とすれば、世界の人類の三分の一はキリスト教徒だということになる) しかし、 カトリック教会 聖公会 プロテスタント 正教会 東方諸教会 など、流派は多岐に分かれている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリスト教の誕生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
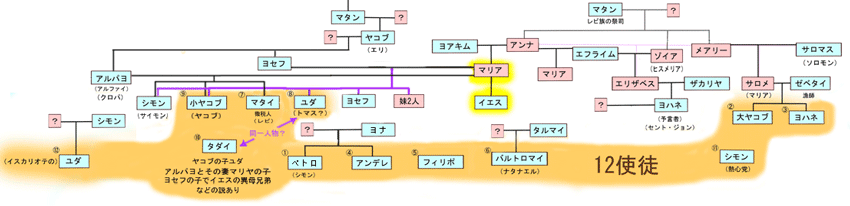 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プトレマイオス朝エジプトなどによる支配を経て、ローマ帝国によってユダヤ(イスラエル)人が支配されているころ、 ソロモンの子孫でナザレ村に住む大工のヨセフの婚約者マリアが、天使から受胎告知を受け処女懐胎。 紀元前4年ごろにイエスが降誕する。 イエス降誕年については、ヘロデ王(アグリッパ1世)の治世末期に産まれたとされていることから、紀元前4年(~紀元前7年)ごろではないかと近年の研究では言われている。 ヨセフと身重のマリアは、ベツレヘムに来ていた。 というのも、ローマ帝国政府のお達しで 「ユダヤ人は自分の故郷で人口調査のための登録をしなさい」 というものがあったから。 ベツレヘムの宿屋は満杯で、やむなく二人は家畜小屋(馬小屋)に宿泊することになった。 そこでマリアは出産し、イエスが降誕する。 天使のお告げを受け羊飼いたちが祝福に駆け付け、東方の博士(占星術の学者)三人(三賢者)も贈り物を持って駆け付けた。 ヨセフ一家は、ベツレヘムからナザレへ戻る。 イエス降誕から二十数年経ったころ、イエスはヨハネから洗礼を受ける。 そしてその後、宣教活動を始める。 ガラリヤ湖周辺で宣教し、数々の奇跡を起こしたという。 イエスがだんだんと有名になってくると、パリサイ(ファリサイ)派の人々(学者や裕福なユダヤ人層)から目を付けられるようになってきてしまう。 弟子たちとエルサレムで(最後の)晩餐を終え、ゲッセマネという地で祈りを捧げたイエスは捕えられてしまう。 裁判が行われ、イエスには死刑が下される。 ゴルゴダの丘にある刑場へ、自分で背負って運んだ十字架に磔にされる。 磔にされたイエスは、絶叫の後、息を引き取った。 イエスがゴルゴダの丘で十字架に磔にされたのは、AD30年頃のことだと言われている。 「ルカによる福音書」では、 『父よ、私の霊を御手に委ねます』 「マルコによる福音書」「マタイによる福音書」では、 『我が神よ、我が神よ、なぜ私をお見捨てになられたのですか』(エリ、エリ、レマ、サバクタニ) と、イエスの最後の絶叫を記している。 ちなみに 福音書 は エヴァンゲリオン という。 三日後、イエスは予言していた通り復活し弟子たちの前に姿を現す。 復活してから40日後、イエスは弟子たちと離れ、オリーブ山で昇天(神の元へ帰る)します。 その後、弟子たちが各地へ散らばり、イエスの教えや奇跡の布教をしていきます。 AD70年頃~ユダヤ戦争の結果としてエルサレム神殿が崩壊したころ~に、キリスト教は独立する。(それまではユダヤ教の一部だった) 313年、ローマ帝国帝王コンスタンティヌスがミラノ勅令(宣言)を発布し、キリスト教をはじめとする全ての宗教を公認。 (拡大するキリスト教を帝国統治に利用しようとする意図があったとされる) その後、キリスト教徒に特権が与えられるようになり、 392年、ローマ帝国皇帝テオドシウス1世はキリスト教を国教と定めた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12使徒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | イエス・キリストの弟子(高弟)12人を指す。 「マルコによる福音書」3章14~20節 『そこで十二人をお立てになった。彼らを自分のそばに置くためであり、さらに宣教につかわし、』 『また悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。』 『こうして、この十二人をお立てになった。そしてシモンにペテロという名をつけ、』 『またゼベタイの子ヤコブと、ヤコブの兄弟ヨハネ、彼らにはボアネルゲ、すなわち、雷の子という名をつけられた。』 『つぎにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、』 『それからイスカリオテのユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。イエスが家にはいられると、』 『群衆がまた集まってきたので、一同は食事をする暇もないほどであった。』 「マタイによる福音書」10章1~4節 『そこで、イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆるわずらいをいやす権利をお授けになった。』 『十二使徒の名は、次のとおりである。まずペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、それからゼベタイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、』 『ピリポとバルトロマイ、トマスと取税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、』 『熱心党のシモンとイスカリオテのユダ。このユダはイエスを裏切った者である。』 「ルカによる福音書」6章13~16節 『夜が明けると、弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選び出し、これに使徒という名をお与えになった。』 『すなわち、ペテロとも呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、』 『マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと、熱心党と呼ばれたシモン、』 『ヤコブの子ユダ、それからイスカリオテのユダ。このユダが裏切り者となったのである。』 と、各福音書に、イエスが弟子の中から十二人を選び出して 使徒 と名付けたということが書かれている。
「マルコ」と「マタイ」では順番が少し違うだけで、12使徒の名前は一緒である。 「ルカ」だけ タダイ が無くて ヤコブの子ユダ が加わっている。 |
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①(シモン/シメオン)ペトロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンデレの兄。 ベトサイダ出身。 ガラリヤ湖で漁をしていた時に、イエスからアンデレとともに声を掛けられ最初の弟子になった。 首座使徒のひとり。 もともとはシモン(シメオン)という名だったが、イエスにより ペトロ と名付けられた。 (他にもシモン/シメオンの名を持つ者が近親にいたための区別のためか?) ペテロ、ペトル、ケファとも。 新約聖書に「ペトロの手紙一」「ペトロの手紙二」がある。 しかし、いずれもペトロ自身の著作ではないとも言われている。 初代ローマ教皇。 ローマ教皇=カトリック教会の最高位。 時代が進むにつれ、次第にバチカンのローマ司教が教皇として力を持つようになっていく。 1929年にバチカン市国が独立国家となり、現在ではローマ法王(教皇)=バチカン市国の国家元首とされている。 イエスが捕縛されるとき、イエスの予言通りにペトロはイエスを三度否認する。 イエス復活の時にはヨハネとともにイエスの墓に駆け付けている。 48年頃、ヤコブがエルサレム教団のリーダーになると、各地で伝道を行うようになった。 44年頃、ヘロデ・アグリッパ1世(ヘロデ王)は初期キリスト教グループを迫害。ペトロはヤコブと同様に捕らえられるが脱出する。 外典「ペトロ行伝」などによると、 その後、ローマで宣教するが、ローマ皇帝ネロの迫害を受け、67年に逆さ十字架に磔にされ没する。 迫害を逃れるためにローマから逃れようとしたペトロは、アッピア街道で前から歩いてくるイエスと出会う。 「主よ、どこへ行くのですか? (Domine quo vadis?/ドミネ クォ ヴァディス?)」 と訊ねると 「あなたが私の民を見捨てるのなら、私はもう一度、十字架に架けられにローマへ」 と答えた。 その言葉を聞いて、ペトロはローマへと戻ることにしました。 イエス様、洒落が利いてるというか、ドラマティックな演出しますね。 イエスが迷うペトロの心を定めるために降臨したのか、ペトロの心の葛藤が見せた幻なのかはわかりませんが、一度ローマから逃げようとしたペトロは思い直してローマへと戻り殺されてしまいます。 ローマ市内のバチカンの丘というところにペトロの墓だと伝えられる場所があり、 326年にローマ帝国皇帝コンスタンティヌス1世によって、その地に教会堂が建てられた。 この地がカトリック教会の本拠地として発展していき、ローマ司教は教皇として力を持つようになっていく。 752年、ローマ教皇は教皇領とされる領土をも持つようになる。 時代とともに教皇領は拡大縮小(ときにはナポレオンによる侵略などもあった)していく。 1506年、サン・ピエトロ大聖堂(聖ペトロの大聖堂/バチカン市国にあるカトリック教会の総本山)着工。(1626年に竣工) 1849年、ローマ共和国が成立すると、教皇(ピウス9世)はそれを警戒してフランスに援助を求め、フランス軍がローマに進駐する。 1860年にはイタリア王国が成立。イタリア王国は軍を進軍させ、教皇領の北部地域を接収。 1870年、フランス軍がローマから撤退すると、イタリア軍は全ての教皇領を接収し教皇領は消滅する。教皇側(カトリック教会)はサンピエトロ大聖堂のあるバチカンの地で引きこもる形になり、イタリア政府との断絶は続いた。 1929年にラテラノ条約(教皇との和解)が締結され、教皇領の権利を放棄するかわりに独立国家バチカン市国となった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
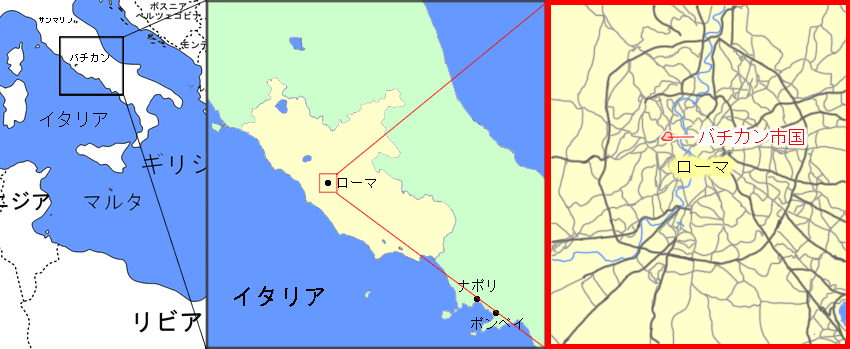 バチカン市国は、イタリア共和国の首都で、ラツィオ州の州都ローマの中にある国だよの図 上の図の、右側の赤線で囲った小さい部分がバチカン市国です。 バチカン市国の国土面積は 0.44平方km で、だいたい東京ドーム10個分の広さ。 ちなみに、 東京ドーム 0.046755平方km(敷地面積) 東京ディズニーランド 0.51平方km USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) 0.54平方km よみうりランド 0.37平方km 東京都千代田区 11.66平方km 東京都中央区 10.21平方km (中央区のほうが狭かったのねw) 埼玉県蕨市 5.11平方km (日本で一番狭い市) 青森県弘前公園 0.492平方km 宮城県青葉山公園 0.405777平方km 東京都皇居 1.15平方km 東京都上野恩賜公園 0.5385平方km 大阪府大阪城公園 1.055643平方km 兵庫県姫路城 2.3平方km 熊本県熊本城公園 0.563平方km なので、バチカン市国の大きさは少し大きめな遊園地や城跡公園などと同じぐらいです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サン・ピエトロ大聖堂の地下には、実際に墳墓があって、 1939年に第260代ローマ教皇ピウス12世が学術調査を依頼すると、その結果、丁寧に埋葬された1世紀ごろの男性遺体が発掘された。 1968年、第262代ローマ教皇パウロ6世が「(その遺体が)ペトロのものであると確認された」と発表。 しかし、真偽のほどは決着がついていない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリスト教徒の方が読んじゃったらものすご~く怒られそうなことを書いちゃうけど、 イエスの一番弟子のペトロは、イエスが捕縛されたときに師を裏切り(三度知らないと言った)、皇帝ネロの迫害が厳しくなってきたときにローマの教徒たちを見捨てようとした。その負い目を引きずりながら生涯を終えた人だったんじゃないですかね? 自分はいざというときに強い心を持てない人間だ。だからこそ、守れなかったイエスを褒め称えたし、ローマの教徒を見捨てようとしたときにイエスの幻影が彼を踏み留めさせたのだと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②(ゼベダイの子)ヤコブ(大ヤコブ)(使徒ヤコブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネの兄。 アルパヨの子ヤコブと区別するため 大ヤコブ とされる。 ガラリヤ湖に停泊中の漁船の中で網の手入れをしていたところ、イエスに呼ばれヨハネとともに弟子になった。 首座使徒のひとり。 44年頃、ヘロデ・アグリッパ1世(ヘロデ王)は初期キリスト教グループを迫害。大ヤコブは捕らえられ処刑される。 エルサレムに埋葬することが困難だったので、弟子たちはこっそりと大ヤコブの遺体を運び出し、船に乗って神の導きに行き先を任せた。すると、船はヒスパニア(現在のスペイン)のガルシア地方に着いたので、その地に大ヤコブを埋葬した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ということは、  大ヤコブの遺体の動向図 赤線は簡易的なルート 大ヤコブの遺体を乗せた船は、エルサレムから地中海を横断。ジブラルタル海峡を抜け北大西洋に出ると、イベリア半島沿岸部を北上しヒスパニア(現在のスペイン)のガルシア地方に到着したことになる。 当時のこのあたりの海流がどういうものだったのかは確かめようもないが、神任せでたどり着ける航程なのだろうか? しかも、船は石の船だったらしい。 あっ! 神任せだからこそたどり着けるのか・・・。石の船でも大丈夫なわけだね。 そこはあまり詮索しないでおこう・・・。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9世紀のイベリア半島(現在のスペイン)では、レコンキスタ(複数のキリスト教国家によるイべリア半島の再征服活動)の最中であった。 そんな中、アストゥリアス王国国王アルフォンソ2世はガルシア地方に版図を拡げていく。 814年、アストゥリアス王国の領地となったガルシア地方で、星に導かれた羊飼いが“奇跡的に”聖ヤコブ(サンティアゴ)の遺骨と墓地と聖遺物を発見する。 その“奇跡的に発見された”の墓地の上に、聖堂、教会が建てられ、都市として発展していった。 現在、サンティアゴ・デ・コンポステーラ(大聖堂)は、エルサレム、バチカンと並ぶキリスト教徒の巡礼地となっている。 そういった経緯から、大ヤコブはスペインの守護聖人とされている。 名前に使われている ジョン ジャック ジェームス ジェイコブ などはヤコブの名に因む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③(ゼベダイの子)(使徒)ヨハネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大ヤコブの弟。 ガラリヤ湖に停泊中の漁船の中で網の手入れをしていたところ、イエスに呼ばれ兄ヤコブとともに弟子になった。 他のヨハネとの区別で 使徒ヨハネ とよばれることもある。 首座使徒のひとり。 新約聖書に「ヨハネによる福音書」「ヨハネの手紙一」「ヨハネの手紙二」「ヨハネの手紙三」「ヨハネの黙示録」がある。 イエスが十字架に磔にされたとき、弟子の中で唯一、十字架の下にいたとされる。 イエス復活の時にはペトロとともにイエスの墓に駆け付けている。 ローマ皇帝ドミティアヌスによる迫害でパトモス島に幽閉されるが、後に釈放され、エフェソス(トルコ西部の小アジアの古代都市で、現在のイズミル県のセルチュク近郊)で没したとされる。 12使徒の中で唯一、天寿を全うした使徒だそうです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④アンデレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペトロの弟。 ベトサイダ出身。 ガラリヤ湖で漁をしていた時に、イエスからペトロとともに声を掛けられ弟子になった。 ビザンティウム初代司教。正教会コンスタンディヌーポリ総主教庁初代主教。 ・アンデレが伝道を行った地域としてルーマニアとロシアがある。 ・ギリシアのアカイア地方で、ローマ総督アイゲアテスの怒りを買い、X字型の十字架(アンデレの十字架)で磔処刑された。 ・アカイアのパトラス司教聖レグルスがアンデレの聖遺物を持ってスコットランドのファイフに移った。 などの逸話から、ルーマニア、ロシア、ギリシア、スコットランドで守護聖人とされている。 名前に使われている アンドリュー アンドレ などはアンデレの名に因む。 ゴルフの発祥地であるスコットランドのセント・アンドリューズは、聖アンデレの名に因んでつけられている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤フィリポ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトサイダ出身。 ヨルダン川の岸辺にいたところを、イエスに声を掛けられ弟子になった。 新約外典に「フィリポによる福音書」がある。 しかし、フィリポの著作ではないとされている。 「フィリポによる福音書」には、マグダラのマリヤがイエスの伴侶だという記述があるという。 ヒエラポリス(現在のトルコ西部の都市)で、二人の娘とともに異教徒に捕らえられ、十字架にかけられ石打ちにされて没した。 名前に使われている フィリップ フィリップス などはフィリポの名に因む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥バルトロマイ(タルマイの子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナタナエルと同一人物とされる。 フィリポとともにアジアやインド宣教を行い、タダイとともにアルメニアで宣教を行う。 アルメニアの地で、生きたまま皮を剥がされるという処刑で没した。 名前に使われている バーソロミュー バルトロメオ などはバルトロマイの名に因む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ナタナエル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルトロマイと同一人物とされる。 ガラリヤのカナ出身。 フィリポからイエスを紹介され弟子になる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦(徴税人)マタイ (レビ)(アルパヨの子/アルファイの子/クロパの子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ帝国(ユダヤ属州)の徴税人だったが、イエスに呼ばれ弟子になる。 『さてイエスはそこから進んで行かれ、マタイという人が収税所にすわっているのを見て、「わたしに従ってきなさい」と言われた。すると彼は立ちあがって、イエスに従った。』「マタイによる福音書」9章9節 「マルコによる福音書」2章14節には、 『また途中で、アルパヨの子レビが収税所にすわっているのをごらんになって、「わたしに従ってきなさい」と言われた。すると彼は立ち上がって、イエスに従った』 「ルカによる福音書」5章27節では、 『そののち、イエスが出て行かれると、レビという名の取税人が収税所にすわっているのを見て、「わたしに従ってきなさい」と言われた。』 という記述がある。 この三つの福音書の内容は同等とみられるため、マタイとアルパヨの子レビは同一人物とする解釈が成り立つ。 ただし、別人説もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私の見解では、同一人物(マタイ=レビ)でいいんじゃないかと思う。 このエピソードが出てくる福音書では、マタイ(レビ)がイエスに従った後、 『それから、イエスが家で食事の席についておられた時のことである。多くの取税人や罪人たちがきて、イエスや弟子たちとともにその席に着いていた。』「マタイによる福音書」9章10節 『それから彼の家で、食事の席についておられたときのことである。多くの取税人や罪人たちも、イエスや弟子たちと共にその席に着いていた。こんな人たちが大ぜいいて、イエスに従ってきたのである。』「マルコによる福音書」2章15節 『それから、レビは自分の家で、イエスのために盛大な宴会を催したが、取税人やそのほか大ぜいの人々が、共に食卓に着いていた。』「ルカによる福音書」5章29節 と、後の記述にも同等とみられる内容がでてくるからだ。 それにしても、聖書は、曖昧な表現になっている部分や、文章としておかしい部分(翻訳のせいかもしれないが)が多いように感じられる。 「マタイによる福音書」の「イエスが家で食事の席についておられた」 という部分ひとつ取っても 「イエスが(自分の)家で食事の席についておられた」 と読めなくもない。(邪推だけど) 大勢が席に着ける食卓がある家に住む取税人(徴税人)マタイ(レビ)。すごい豪邸に住んでいたんですね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マタイとアルパヨの子レビが同一人物だとすると、アルパヨの子とされている小ヤコブ(小ヤコブの項参照)とマタイ(レビ)は兄弟(異母兄弟の線もあるが)だということになる。 そして、 (義人)ヤコブと小ヤコブが同一人物だとする説もあり(義人ヤコブの項参照)、 それも踏まえれば、(義人)ヤコブはイエスと兄弟(もしくは従兄弟)とされているので、 イエス、(義人/小)ヤコブ、マタイ、ヨセフ、ユダ、シモン、その他にいる姉妹 が兄弟姉妹(もしくは従兄弟従姉妹)ということになる。 マケドニア(現在のギリシア北部から北マケドニア周辺のバルカン半島中央地域)、 ペルシア(現在のイラン。メソポタミア地域の東)、 (現在の)エチオピア(東アフリカの地域。時代的にはアクスム王国かそれ以前) で伝道を行ったとされる。 「黄金伝説(聖者の物語)」(12世紀に完成したとされるキリスト教の聖人伝集)に、 『エチオピアのナダベルの町で宣教していた時に、ヒルタコス王を怒らせてしまって、王が送った刑吏によって背後から剣で刺されて没した。 その後、遺骨はイタリア南部のサレルノという町の大聖堂に運ばれた。』 とあるそうだ。 また、ペルシアのヘリオポリス、トルコのヒエラポリスで没したという伝承もあるらしい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マタイの最期の地として ペルシアのヘリオポリス という地名が出てくる。 調べてみると、ペルシア=現在のイランにはヘリオポリスという地名は見当たらない。 エジプトのカイロ北東部(エジプト陸軍士官学校やカイロ国際航空の近く)にその名を見つけることができる。 世界大百科事典 第2版(株式会社平凡社)によれば、 『カイロの北東郊外にある古代エジプトの太陽神信仰の中心地のギリシア名。 古代エジプト名はイウヌウIunu,聖書地名のオンOnに相当する。 太陽神(アトゥムおよびラー)を宇宙創造神とする〈ヘリオポリス神学〉は,オシリス神話をも取り込んでエジプトの宗教思想に深い影響を与え,他の大神はラーとの習合により太陽神,創造神の権威を主張し,イクナートンのアテン信仰の源泉ともなった。 神域に奉納された太陽神の象徴オベリスクは1本を残して海外に流出し,ローマ,ニューヨーク,ロンドンの広場を飾っている。』 とある。 読んでもあまり内容が頭に入ってこない文章だが。 紀元前30年に古代エジプト(プトレマイオス朝)が古代ローマ(共和制ローマ)に滅ぼされた後、 ラーおよびアトムはギリシアの太陽神ヘリオスと同化され(または置き換えられて)、 太陽神信仰の都市イウヌウはヘリオポリスと呼ばれるようになった。 のだろうか? また、 エジプトの太陽神ラーは主神であったためにローマ神話の主神ユピテル(ギリシア神話での絶対神ゼウス)との同化(または置き換え)が行われ、 神殿はユピテル神殿の名を冠することに なったのであろう。おそらく。 もう少し検索を続けると、 シリアのベイルートとダマスカスの間にあるザバダニから北上したところにバールベックという古都(遺跡)があって、この地も古代ギリシア人たちからヘリオポリス(太陽の都)と呼ばれていたということが解った。 『レバノンのベイルート東方約85㎞、レバノン山脈とアンチ・レバノン山脈に挟まれたベカー高原中央北部にあるオアシスをもつ避暑・観光都市。人口約1万人程度。 バルベクとも書かれ、アラビア語で正しくはバーラバックBa'labakk。古代宗教都市の遺構で知られる。 〈ベカーの主〉を意味するその名前からファニキア起源と考えられるが、アレクサンドロス大王の征服後、フェニキアのハダド神とギリシアのゼウス神が習合することによって隆盛し、ヘリオポリスHeliopolisと改名された。』 世界大百科事典 第2版(株式会社平凡社) だそうな。 古代ギリシアのアルゲアス朝マケドニア王国のバシレウス(王の意味)であるアレキサンドロス3世(紀元前356年7月20日~紀元前323年6月10日)は、紀元前330年頃にアケメネス朝ペルシア帝国を滅亡させている。 アレキサンドロス大王の大遠征において征服されたバーラバック(バールベック)の地がヘリオポリスに改名されたのであれば、同じくエジプトでもアレキサンドロス大王に征服されたときに、太陽神信仰都市がヘリオポリスに改名された可能性は高い。 ってことは、古代ローマ時代(紀元前30年頃)よりももっと古い時代(紀元前300年頃)にヘリオポリスに改名されたのかもしれない。 アレクサンドロス大王は、征服した地に自分の名に因んで命名したと伝えられる アレクサンドリア という都市が複数ある。 古代ギリシアのアルゲアス朝マケドニア王国ってとこは、都市の改名好き国家だったのかもしれないですね。(どーだかねw) ちなみに アレクサンドロス(ギリシア語)/アレキサンダー(英語)/イスカンダル(アラビア語、ペルシア語)です。 紀元前525年、エジプトはアケメネス朝ペルシアに征服される。 紀元前330年頃、アレクサンドロス大王に征服される。プトレマイオス朝が成立し太陽神信仰都市イヌトゥは、ギリシャ語のヘリオポリスに改名。 紀元前30年、ローマ帝国の属州となる。 なので、 ペルシアのヘリオポリス=エジプトのヘリオポリスではないぢゃないかっ! で、も一度、ペルシア(現在のイラン)にヘリオポリスを探してみる・・・ が、 やっぱないっ! ペルセポリスの間違いなんじゃないか? と、 ペルシアのヘリオポリスが解らず仕舞いで終ったところで。 wikipediaに「ファラオの運河」という図が載っている。(「スエズ運河」の「古代の運河」項目) その図にも ヘリオポリス の文字が書かれている。 ブバスティスからグレートビター湖に真横に伸びた運河の間に ヘリオポリス が位置付けられている。 これって、 現在の ヘリオポリス の位置とずいぶん離れている。 どっちが正解なのだろう? ヘリオポリスは、古代エジプトでは大都市だったらしいので、 現在のヘリオポリスの位置と「ファラオの運河」図に書かれたヘリオポリス その二つを含めた広範囲な大都市だった可能性は・・・ ・・・ ・・・ この二つのヘリオポリスを含む範囲としてしまうと あまりにも広範囲で 小国家ぐらいの規模になってしまうではないか・・・。 一時、この辺りはヘリオポリスという国家が樹立された? さすがにそれはないだろう・・・。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia「スエズ運河」の項目の「古代の運河」を読むと、 「エジプト誌」(ナポレオン・ボナパルトが1798年~1799年のエジプト遠征時に、フランス軍を指揮して行った調査結果をまとめたもの)に 「紅海から北へ伸び、そしてナイル川を目指して西へ転じる古代運河の発見について説明する詳細な地図が添付された」 「古代エジプトのブバスティス、アヴァリス(ペル・ラメセス)、ビションを結ぶ運河(東西を結ぶ運河の遺構)を発見した」 という記述があるらしい。 おそらく、この「エジプト誌」に添付された詳細な地図を参考にして「ファラオの運河」の図は作られたのだと思う。 図に書かれた文字がたぶんフランス語なので。 残念ながら、今のところ「エジプト誌」を調べる術がないのだが、いつの日かそういう機会が得られたら追記したいと思います。 そして、 古代ギリシアの歴史家ヘロドトス(紀元前4世紀の人)の著書「ヒストリア(歴史)」には、 「紀元前600年頃にネコ2世は、ブバスティスとピション(ヘリオポリス)を東西に貫きワジ・トゥミラートを通る運河建設に着手した」 「ネコ2世の運河は、古代エジプトを征服したペルシアのダレイオス1世の手によって完成された。当時、ヘリオポリス湾と紅海の間にはグレートビター湖のちょうど南に位置したシャルーフの町近郊を通る自然の水路があった。しかしこれはシルトで埋まっていたため、ダレイオス1世は浚渫させて船の航行を可能にした」 という記述があるらしい。 ネコ2世=エジプト第26王朝の第2代目ファラオ。紀元前600年頃~紀元前595年。 ダレイオス1世=アケメネス朝ペルシアの王。紀元前550年頃~紀元前486年。 浚渫=(しゅんせつ)水底の土砂などをさらって取り去る土木工事のこと。 上記の「ピション(ヘリオポリス)」という部分が引っかかる。 ヘロドトスの「歴史」自体に(ヘリオポリス)と書き込まれているのか、こちらも今のところ入手していないので、確かめることができたら追記したいと思う。 ピション=ヘリオポリス だとすると、 ブバスティス~ピション(ヘリオポリス)湾~ワジ・トゥミラート川~グレートビター湖の南のシャフール町近郊を通る水路~紅海 というルートになる。 出てきた地名を探ってみると |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ブバスティス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のザガジグ郊外 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アヴァリス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のテル・アル=ダバア遺跡付近(ペル・ラメセス/ピラメセス)で、ヒクソス(外国の王の意味だとか?)人によって建てられたエジプト第15王朝の首都だったところ。 かつてはタニス(テル・アル=ダバア遺跡の北に位置する古代都市)遺跡付近がそうだと考えられていた。 しかし、「エジプト誌」の『ブバスティス、アヴァリス(ペル・ラメセス)、ビションを結ぶ運河』を考えたとき、アヴァリスの位置が現代のペル・ラメセスよりももっと南(現在のザガジグと同じぐらいの経度)のほうが適合性が高いと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ビション/ピション (ヘリオポリス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の土地にその名は見当たらないが、ザガジグ、ペル・ラメセスから伸びたところなのであろう。 ピトム(ヘブライ語)、ペル・アトムまたはヘロノポリス(ギリシア語)と呼ばれる古代都市も同じものだとされる。 場所については複数の説があるようで特定はされていない。 ザガジグ、ペル・ラムセスから伸びたところであれば、ティムサーハ湖北部に伸びる運河が現在もみられるので、その付近と考えるのが無難なのではないだろうか? もしくは、「ファラオの運河」図にあるヘリオポリス(「エジプト誌」にある記述『ビション』)がヘロドトスの「歴史」にある記述『ピション(ヘリオポリス)』と同一で正しいのかもしれない。 現在のカイロ近くにあるヘリオポリスはそれよりも新しい時代になってからそう呼ばれるようになったのかもしれない。 もしくは、ヘリオポリスという名は「太陽信仰の都市」「太陽信仰の神殿がある都市」という意味ならば、同名の地が複数存在していても不思議はない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ワジ・トゥミラート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ナイル川」を検索してみると、 過去にはもっと多くの分流があって、肥沃なナイル川デルタ地帯を形成していたということが解る。 毎年起こっていた洪水の対策(洪水は1970年完成のアスワン・ハイ・ダム完成によって、ほぼ完全に防げるようになった)や運河の形成などの治水事業によって分流の多くは消滅した。そのひとつがワジ・トゥミラートなのだという。 なので、ワジ・トゥミラートというのは過去に存在したナイル川の分流で、いつの頃か消滅してしまったのだということだ。 ナイル川から伸びた川だったということ以外は特定できていないようだが、カイロから北東に伸びて、ザガジグ近郊で進路をほぼまっすぐ東に変えて、ティムサーハ湖の北側に入り込む水路(運河/川?)が現在の地図上で確認できる。ワジ・トゥミラート川は、この水路(運河/川?)と同じようなルートだったのではないだろうか? または、現在残る水路(運河/川?)がワジ・トゥミラート川そのもので、実は消滅していなかった。というオチはないだろうか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ヘリオポリス湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おそらく、都市のヘリオポリスの近くだと思われるが、ヘリオポリスは内陸なので湖(もしくは川)の湾ということだろうか? 湾というだけにそこそこの広さはあったんだとは思うのだが・・・。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・紅海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の紅海と同じだが、古代では入り江はもっと北部に入り込んでいたと思われる。 時代をさかのぼると、もしかしたら地中海と繋がっていて、アフリカ大陸とアラビア半島を分けていた分けていた。ということもありえるのではないだろうか?プレートテクニクスなんかを調べればわかるかもしれないので、わかり次第追記したいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・グレートビター湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在もグレート・ビター湖はその名を残し存在している。形、大きさ、位置は多少変化しているはずである。 紅海と繋がっていたり、飲み込まれていた可能性も考えられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・グレートビター湖のちょうど南に位置したシャルーフの町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のシャルーフの町は特定できなかった。しかし、グレート・ビター湖は今も存在しているので、そのちょうど南であることは間違いない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図で表してみるとこんな感じ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナポレオンの「エジプト誌」の 「紅海から北へ伸び、そしてナイル川を目指して西へ転じる古代運河」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時代を遡れば遡るほど、紅海は今よりも北に延びていただろうから、起点は現在の紅海北岸よりも北に位置していたであろう。 紅海から北へ伸びた運河が、あるところからナイル川を目指して西へ進路を変えていた。 ということなので、上の図のオレンジ線~wikipedia「ファラオの運河」図~で正解なのだと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じく、ナポレオンの「エジプト誌」の 「ブバスティス、アヴァリス(ペル・ラメセス)、ビションを結ぶ運河。(東西を結ぶ運河の遺構)」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代のブバスティス(ザガジグ)、アヴァリス(ペル・ラメセス)、ピション(ヘリオポリス)を結ぶと、東西には貫けずに、山なりの形(北東へ伸びてから南東に向かう)のルート(上の図の緑色の線)になってしまう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘロドトスの「歴史」の 「ブバスティスとピション(ヘリオポリス)を東西に貫きワジ・トゥミラートを通る運河」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代のザガジグと現代のヘリオポリス(上の図の黒字で示した〇のついた都市名)を結ぶと東西にはならず、北東になってしまう。 ピションの位置をザガジグと同じぐらいの経度に存在した都市(上の図の紫字のピジョン?から伸びた線と点線、wikipedia「ファラオの運河」図にあるヘリオポリスの位置を示したオレンジ色文字のヘリオポリス)だとし、ワジ・トゥミラートを現在もザガジグと同じぐらいの経度で横断している水路(運河/川?)(上の図のワジ・トゥミラート文字が指す青色の太い線)だすると、東西を貫く運河(上の図のオレンジ色の線、wikipedia「ファラオの運河」図の運河の位置)だといえる。 現在のカイロ近くにあるヘリオポリス(上の図の黒字)が新しい時代になってからそう呼ばれるようになったのか、ヘリオポリスという名の都市が複数存在していて、「歴史」に出てくるヘリオポリスが現代のカイロ近くにあるヘリオポリス(上の図の黒字)と別の都市だとすると、ブバスティスとヘリオポリスを東西に貫く運河の存在はありえるものとなる。 「太陽信仰の都市」「太陽信仰の神殿がある都市」という意味のヘリオポリスは、同名の地が複数存在していてもなんの不思議はない。(現に他の国にも存在しているわけだし) 現代のザガジグと現代のヘリオポリス(上の図の黒字で示した〇のついた都市名)の間を東西に貫くワジ・トゥミラートを通る運河 と解釈すれば、 ワジ・トゥミラート川も南に位置する(上の図のワジ・トゥミラート文字が指す青色の細い線)ことになる。 無くもないかもしれないが、可能性は低いと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘロドトスの「歴史」の 「ヘリオポリス湾と紅海の間にはグレートビター湖のちょうど南に位置したシャルーフの町近郊を通る自然の水路」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都市であった古代のヘリオポリスであれば、そこを通る運河(もしくは川)は船を停泊させるために整備されていただろうから、湾を形成していてヘリオポリス湾と呼ばれていたのであろう。 そのヘリオポリス湾と紅海の間にある自然な水路とは、ワジ・トゥミラートのことだろうかね?そんな気がする。 シャルーフの町はグレートビター湖の南。(シャフールの町?文字が指す紫の範囲辺りのどこか) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マタイの最後の地として、 ・ペルシアのペルセポリス(ヘリオポリスという部分が間違いだった場合) ・エジプトのヘリオポリス(ペルシアという部分が間違いだった場合) ・エチオピア(ヒルタコス王の時代)(「黄金伝説」の記述)(アクスム王国の中心地だった地に現代でもアクスムという街がある) ・トルコのヒエラポリス(フィリポとの混同?という気もするが) の四候補が挙がる。 どこが正しいのか確定はされていないようだが、遺骨はイタリア南部のサレルノという町の大聖堂に運ばれたという。 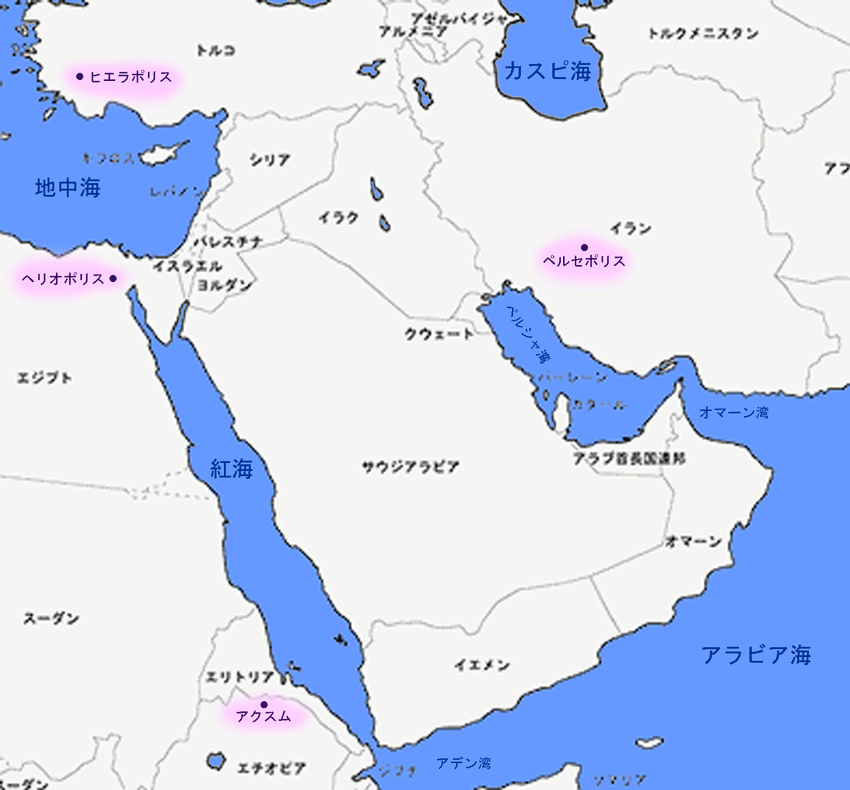 マタイの最期の地4候補の図 マタイだけでずいぶんと尺を取ってしまった・・・。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧トマス(ユダ)(ディディモ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トマス(アラム語)もディディモ(ギリシア語)も双子を意味する言葉であるという。 本名はユダ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福音書の一部の写本や外典に「ユダ・ディディモ」の記載があるらしく、 それを踏まえて、「ユダが本名でトマス(ディディモ)が綽名である」という解釈が成り立つ。 つまり、本名はユダであったが、ユダ族の流れを組む人たちの中での生活圏ではユダの名を持つ人が多かった。 そのため、誰かと双子だったユダは綽名(通称名)でトマス(ディディモ)と呼ばれたということらしい。 イスカリオテのユダの場合は、出身地ではないガラリヤで生活していたことから、「イスカリオテ(イシュ・ケリヨト/ケリヨトの人)の」(この場合は出身地)という冠名が付いたのだろう。 例えば、 三人の太郎さんが近所で暮らしている。 一人は大工だったので「大工の太郎さん」と呼ばれ、 一人は大阪出身だったので「大阪の人太郎さん」と呼ばれ、 一人は双子だったので「双子の太郎さん」と呼ばれた。 後に三人は、三人とも大の蒲焼好きだったことから「蒲焼さん太郎」と皆から呼ばれるようになった。 という感じ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエスと双子の兄弟? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「マタイによる福音書」に、 『そして郷里に行き、会堂で人々を教えられたところ、彼らは驚いて言った、「この人は、この知恵とこれらの力あるわざとを、どこで習ってきたのか。』13章54節 『この人は大工の子ではないか。母はマリヤといい。兄弟たちは、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。』13章55節 という記述がある。 よって、イエスにはユダという兄弟がいた。ということが解る。 トマスの本名がユダだとしたら、イエスの兄弟のユダと同一人物なんじゃないか? という説が浮かび上がる。 そしてまた、 トマス(ディディモ) は双子を意味するので、イエスとは双子の兄弟だったのではないか? と発展させてしまうのが人というものでありんす。 しかし、神の子イエスと双子の兄弟というのは・・・。 だとしたら、イエス降誕の話に「双子」の逸話が無ければおかしいのではないか? イエスと双子 よりは、イエスの兄弟として名が挙がる ヤコブ、ヨセフ、シモン、または姉妹二人 の中の誰かと 双子(トマス)だったユダがいた というほうがしっくりくる感じがする。 なので、 イエスと双子の兄弟という説は可能性が低い と思います。 仮に、 イエスの兄弟=トマス だとすると イエスの兄弟=タダイ説 は否定される。 だって、トマスとタダイは同一人物ではありえないし(イエスが選んだ12使徒で別々に名が挙がっている)、 イエスの兄弟にユダの名はひとりなので。(ん?ひとりって決まってたっけ?) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新約外典に「トマスによる福音書」がある。 しかし、トマス自身の著作ではなく、トマス派の誰かが書いたのであろうとされている。 72年12月21日、宣教地のインドで没したとされる。 名前の ジュード はユダの名に因む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ヤコブ(小ヤコブ)(アルパヨの子/アルファイの子/クロパの子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼベダイの子ヤコブと区別するため 小ヤコブ とされる。 (義人)ヤコブと同一人物とするなら、エルサレム教会の初代総主教。 マタイの兄弟。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「マルコによる福音書」3章18節に 『つぎにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、』 という記述があるので、ヤコブはアルパヨの子であることが解る。 また、「マルコによる福音書」2章14節には、 『また途中で、アルパヨの子レビが収税所にすわっているのをごらんになって、「わたしに従ってきなさい」と言われた。すると彼は立ち上がって、イエスに従った』 という記述があり、レビとマタイは同一人物とする解釈がある(マタイの項参照)ことから、ともにアルパヨの子であるヤコブとマタイは兄弟(異母兄弟の可能性もあるが)だということになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルパヨ(アルファイ/クロパ)とマリヤの子。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ヨハネによる福音書」19章25節に 『さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、母の姉妹と、クロパの妻マリヤと、マグダラのマリヤとが、たたずんでいた。』 とある。 アラム語のクロパは、ギリシア語ではアルパヨ(アルファイ)となるので、クロパ=アルパヨ=アルファイ、その妻はマリヤ。その子にヤコブとマタイの兄弟(異母兄弟の可能性はあるが)がいたことになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエスの兄弟(従兄弟)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小ヤコブと(義人)ヤコブが同一人物とする説がある。(義人ヤコブの項参照) それを踏まえれば、(義人)ヤコブはイエスと兄弟(もしくは従兄弟)とされているので、イエス、(義人/小)ヤコブ、マタイ(ヤコブと同じ父アルパヨの子レビ)、ヨセフ、ユダ(トマス?)、シモン、その他姉妹が兄弟姉妹(もしくは従兄弟従姉妹)ということになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新約聖書の「ヤコブの手紙(ヤコブ書)」があるが、ヤコブという名の他の人物か、ヤコブの弟子によるものではないかとされている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○(義人)ヤコブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエスの弟(または従兄弟)。 小ヤコブと同一人物とする見方もある。 エルサレム教会の初代総主教。 新約聖書に「ヤコブの手紙(ヤコブ書)」がある。しかし、著者については、複数人いるヤコブという名の人物の誰かは特定されていない。 イエスが処刑され復活した後に、兄弟(や血縁者)と一緒にエルサレム教団に参加する。 48年頃、ペトロに代わりエルサレム教団の最高指導者となる。 62年、石打ちの刑に処され没する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤコブについてのまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「マルコによる福音書」に 『またゼベダイの子ヤコブと、ヤコブの兄弟ヨハネ、彼らにはボアネルゲ、すなわち、雷の子という名をつけられた。』3章17節 『つぎにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、』3章18節 とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これは、イエスが12使徒を立てたときに呼び寄せたメンバーの名で、12使徒に選ばれた二人のヤコブは、ゼベダイの子ヤコブとアルパヨ(アルファイ/クロパ)の子ヤコブであることが解る。 二人を区別するために、ゼベダイの子は大ヤコブ、アルパヨ(アルファイ/クロパ)の子は小ヤコブと呼ばれている。 そして、大ヤコブと小ヤコブは同じヤコブの名だが別人。父親の名も違うことが解る。 マタイについても、「マルコによる福音書」にある『アルパヨの子レビ』=マタイ説はスルーされて、 アルパヨの子マタイ とは呼ばれていない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「マタイによる福音書」にイエスの兄弟(もしくは従兄弟)として「ヤコブ」の名が記されている。 『そして郷里に行き、会堂で人々を教えられたところ、彼らは驚いて言った、「この人は、この知恵とこれらの力あるわざとを、どこで習ってきたのか。』13章54節 『この人は大工の子ではないか。母はマリヤといい。兄弟たちは、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。』13章55節 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なので、イエスにはヤコブという名の兄弟(もしくは従兄弟)がいたことが解る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「マルコによる福音書」にも (イエスの教えを聞いた多くの人々は驚いて言った。「)『この人は大工ではないか。マリヤの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。またその姉妹たちも、ここにわたしたちと一緒にいるではないか」こうして彼らはイエスにつまずいた。』6章3節 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と、同様の記述がある。 誤写なのか何なのか分からないが、ヨセフがヨセと書かれているようだが、同一人物であろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「マルコによる福音書」の続きには、 『また、遠くの方から見ている女たちもいた。その中には、マグダラのマリヤ、小ヤコブとヨセとの母マリヤ、またサロメがいた。』15章40節 『マグダラのマリヤとヨセの母マリヤとは、イエスが納められた場所を見とどけた。』15章47節 『さて、安息日が終わったので、マグダラのマリヤとヤコブの母マリヤとサロメとが、行ってイエスに塗るために、香料を買い求めた。』16章1節 「マタイによる福音書」でも 『その中には、マグダラのマリヤ、ヤコブとヨセフとの母マリヤ、またゼベダイの子たちの母がいた。』27章56節 という記述がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小ヤコブとヨセ(ヨセフ)の母はマリヤだということが解る。 小ヤコブとヨセ(ヨセフ)は兄弟ということで、「マルコによる福音書」6章3節でイエスの兄弟だと言われているヤコブは小ヤコブのことになる。 となると、母マリヤとは聖母マリヤのことになる。 古代のユダヤでは、夫が死去した場合に妻は夫の兄弟の妻になるしきたりがあったらしい。 聖母マリヤの夫ヨセフが死んだ後、聖母マリヤはアルパヨ(アルファイ/クロパ)と再婚した。という発想も出てくる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ヨハネによる福音書」には、 『さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、母の姉妹、クロパの妻マリヤと、マグダラのマリヤとが、たたずんでいた。』19章25節 の記述がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロパ(アラム語)は、ギリシア語のアルパヨ(アルファイ)。 なので、 ここでは、 聖母マリヤとクロパ(アルパヨ/アルファイ)の妻マリヤは別人として描かれている。 クロパ(アルパヨ/アルファイ)に、聖母マリヤと同じ名のマリヤという先妻(もしくは後妻)がいたとすれば、複数のマリヤの存在の辻褄は合う。 あーもうっ!ぐちゃぐちゃやないかーいっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩タダイ (ヤコブの子ユダ?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タダイはヤコブの子ユダ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『ピリポとバルトロマイ、トマスと取税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、』「マタイによる福音書」10章3節 『熱心党のシモンとイスカリオテのユダ。このユダはイエスを裏切った者である。』「マタイによる福音書」10章4節 『つぎにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、』「マルコによる福音書」3章18節 『それからイスカリオテのユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。イエスが家にはいられると、』「マルコによる福音書」3章19節 「マタイ」と「マルコ」の「福音書」では、 アルパヨの子ヤコブ の次に タダイ の名が挙げられている。 『マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと、熱心党と呼ばれたシモン、』「ルカによる福音書」6章15節 『ヤコブの子ユダ、それからイスカリオテのユダ。このユダが裏切り者となったのである。』「ルカによる福音書」6章16節 「ルカによる福音書」では、 タダイ の名は出てこずに シモン の名の次に ヤコブの子ユダ と書かれている。 そして、最後に イスカリオテのユダ の名が書かれているのは3つの「福音書」とも同じだ。 タダイ=ヤコブの子ユダ ということなのか? な~んとなくの直感だが、「ルカによる福音書」の 『ヤコブの子ユダ』 という部分が誤写なのでは?という気がする。 『アルパヨの子ヤコブ』と『イスカリオテのユダ』が混ざって『ヤコブの子ユダ』となってしまい、タダイの名は書き損じてしまったのではないだろうか? 文法の違いなどの影響もあるのかもしれない。 ま、私には検証のしようもないことだけど。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤコブの子ユダ=タダイ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮に『ヤコブの子ユダ』というのが誤写や書き損じではなく、 ヤコブの子ユダ=(ヤコブの子)タダイ だとして考えてみる。 どのヤコブの子なのだろう? という疑問が出てくる。 んで、 ユダ(タダイ)の父を探せ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエスの養父ヨセフの父ヤコブ(イエスの義祖父) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この場合、ユダ(タダイ)はイエスの伯父(叔父)になる。 ユダ(タダイ)は他の弟子に比べて年齢が若かったらしいので、この線は可能性が低いだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼベダイの子)大ヤコブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もしそうだとすれば、ヨハネの甥っ子ということになる。 可能性はあるのかもしれないが、おそらく聖書にはそれを匂わせる記述はない。したがって、この線も厳しそう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アルパヨの子)小ヤコブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢が近すぎると思うし、おそらく聖書にはそれを匂わせる記述はない。この線も消える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエスの兄弟(親族)? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエスの兄弟のヤコブ(祖父と同名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエスの兄弟に名が挙がるヤコブが、イエスよりも年齢が上だったら可能性はあるかもしれない。 そうなると、ユダ(タダイ)はイエスの(義理の?)甥っ子ということになる。 そして、イエスの兄弟のヤコブは小ヤコブと同一人物の可能性もある。 ってことは、レビ(マタイ)、サイモン(シモン)は小ヤコブの兄弟なので、この二人もユダ(タダイ)の伯父(叔父)となる。 しかし、イエス、小ヤコブ(ヤコブ)、レビ(トマス)、サイモン(シモン)とユダ(タダイ)の関係性がはっきりと聖書に書かれてはいないので、この線も微妙だと言える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ってなると、 『ヤコブの子ユダ』というのは、やはり、誤写や書き損じの可能性は高いのかなぁ。 ただ、この『ユダ』という名前も面倒な名前で、裏切り者のユダを筆頭に、イエスの兄弟にもユダがいる。 おそらく、ユダ族に多い名前なのだろう。 (キリスト教が広まるにつれて避けられるようになった名前ではあるだろうけど) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエスの兄弟のユダ=タダイ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエスの兄弟にユダの名があり、このユダとタダイを同一視する説もある。 ただし、イエスの兄弟ユダにはトマスと同一人物とする説もある。(トマスの項参照) アルパヨ(アルファイ/クロパ)は、聖母マリヤの夫ヨセフの兄弟(実際にそういう伝承もあるアルパヨの項参照)で、ヨセフの死後、聖母マリヤはアルパヨ(アルファイ/クロパ)と再婚した。 ~古代ユダヤでは、レビラト婚といわれる「(子供がいないまま)夫に先立たれた妻は、夫の兄弟縁者と再婚する義務」があった。(ただし、存命中の兄弟の妻との肉体関係は禁止されていた)~ なので、 イエスに兄弟姉妹がいたとされているが、 ・ヨセフと聖母マリヤの間にできた子(イエス生誕後になるので、全員イエスの弟妹) ・アルパヨと聖母マリヤの間にできた子(こちらもイエス生誕後になるので、全員イエスの弟妹) ・アルパヨと他の妻との間にできた子(すでアルパヨがに妻帯者だった場合は、イエスより年上の子/兄姉の可能性もある) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古代ユダヤでは一夫多妻制だったと思われるので、アルパヨが複数の妻を持つことは可能であっただろう。すでに妻帯者だったアルパヨが、レビラト婚で兄ヨセフの妻マリヤと結婚したり、マリヤを妻にした後で他の女とも結婚したということは実にあり得る話ではある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と、3パターンが考えられる。 そうしてみると、 イエスの兄弟ユダ=タダイ というのもありえそう。 ・・・「ヤコブの子」というところを都合よく払拭すれば・・・だが。 ・ヤコブという男との間にユダ(タダイ)を儲けた女が、ヤコブに先立たれて、ヤコブの兄弟縁者のアルパヨと再婚。 その後、夫ヨセフを亡くした聖母マリヤもアルパヨと再婚することで、ユダ(タダイ)はイエスと(義理の)兄弟になる。 というパターンも考えられる。 そして、 ・イエスの(義)祖父ヤコブがアルパヨと兄弟だったとしたらもっとしっくりくる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤコブの死によって、兄弟のアルパヨはヤコブの妻と子らを迎えることになる。 ヤコブの子ヨセフが死亡したことで、ヨセフの妻聖母マリヤとその子らをヨセフの叔父(または伯父)であるアルパヨが引き取った。 そうして、 ヨセフの子ユダ(タダイ) と 聖母マリアの子イエス は兄弟になった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と、無理やりっぽく力説すれば、一応は筋が通る。 また、「ヤコブの子」は「ヤコブの孫」の誤写だとすれば、 イエスの兄弟ユダ=タダイ はもっと無理のない説になる。 まあ、もっとも、聖書にはそんな記述は見当たらないと思うんで、妄想に過ぎないんですけどね。 「アルパヨはヨセフの弟」っていう逸話(アルパヨの項参照)はあるんだけど。 いろいろ考えましたが、 やっぱ、「ルカによる福音書」の『ヤコブの子』部分が誤写などによる間違いなんじゃないでしょうかね? ただ、タダイは「アルパヨとその妻マリヤの子」「ヨセフの子でイエスの異母兄弟」という伝承もあるようだ。 「アルパヨとその妻マリヤの子」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この場合、妻マリヤが聖母マリヤなのか他のマリヤなのか分からない。 聖母マリヤだった場合は、先に述べているようにアルパヨとレビラト婚したのであろう。 他のマリヤの場合、アルパヨにはマリヤという名の妻が複数人いたことになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ヨセフの子でイエスの異母兄弟」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この場合、ヨセフには聖母マリヤのほかに妻がいたことになる。 聖母マリヤとの婚約前にヨセフに妻がいたのだとしたら、聖書にその記述があってもいいとは思うのだが、ないということは、ほかの妻がいたとしても聖母マリヤとの結婚後ということだろうか。 イエスのその生涯が30~40年ということ、ヨセフの没年がイエスの没年と同じ頃(諸説あり)だということを考えると、イエスが産まれた後に聖母マリヤのほかに妻を儲け、子供も授かった。としてもおかしくはない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この二つの逸話は、どちらも「タダイはイエスの異母兄弟もしくは異父兄弟または親族」となるものだが、後付け感は否めない。 どのみち、イエスの兄弟のユダ=タダイ なのであれば、 イエスの兄弟=トマス説 は否定される。 だって、タダイとトマスは同一人物ではありえないし(イエスが選んだ12使徒で別々に名が挙がっている)、 イエスの兄弟にユダの名はひとりなので。(ん?ひとりって決まってたっけ?) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・聖書に他の記述がないヤコブの子。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ルカによる福音書」の『ヤコブの子』が間違いではなく、ヤコブの子ユダ=タダイ だとして、 ヨセフの父ヤコブ(イエスの義祖父)ではなく、 大ヤコブの子でもなく、 小ヤコブの子でもなく、 ヨセフの子のヤコブ(イエスの義兄弟)の子でもない、 まったく別のヤコブという人の子がユダ(タダイ)だったとしたら、一番しっくりくるパターンなのかもしれない。 そうなると、イエスと兄弟ではなくなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新約聖書に「ユダの手紙」がある。 敗北者の守護聖人とされる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪熱心者(熱心党員/熱心党)のシモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝道地、エジプト、ブリテン島、ペルシア、いずれかの地で没したとされる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑫(イスカリオテの)ユダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新約聖書の「ユダの手紙」、外典「ユダの福音書」の著作者は別人だとされている。 イエス・グループの会計係だった。 イエスを裏切ったのちに首をつって自殺した。 名前に使われている ジュード はユダの名に因む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑫マティア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスカリオテのユダの自殺で欠員ができたため12使徒に選ばれた。 エルサレムでユダヤ人の手によって石打の刑にあい、斬首された。という伝説が残っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○(アリマタヤの)ヨセフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イエスの遺体をピラト(ユダヤ属州総督)に願い出て引き取ったとされる。 「マタイによる福音書」では「金持ちでイエスの弟子」 「マルコによる福音書」では「身分の高い議員」 「ルカによる福音書」では「神の国を待ち望んでいた」「善良で正しい人」 「ヨハネによる福音書」では「イエスの弟子でありながらユダヤ人を恐れてそのことを隠していた」 と記されている。 イエスの遺体を引き取ったあと、亜麻布で包み、香料とともに墓(洞窟)に葬った。 イエスの血を受けた聖杯を持ってイギリスの渡ったという伝承もある。(聖杯伝説) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○パウロ(サウロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元はファリサイ(パリサイ)派で原始キリスト教徒を迫害していたが、ダマスコへ向かう地で天の光(天の一撃)を受けて目が見えず食事も摂れない体になってしまう。アナニアというキリストの弟子の手によって救われ、洗礼を受ける。 新約聖書の書簡(~の手紙)はパウロの著作だと言われていた。 が、現在では、 「ローマの信徒への手紙」「コリントの信徒への手紙一」「コリントの信徒への手紙二」「ガラテヤの信徒への手紙」「フィリピの信徒への手紙」「テサロニケの信徒への手紙一」「フィレモンへの手紙」はパウロの著作であろう言われている。 「エフェソの信徒への手紙」「テサロニケの信徒への手紙二」「コロサイの信徒への手紙」「テモテへの手紙一」「テモテへの手紙二」「テトスへの手紙」については、研究者によって意見が分かれている。 「ヘブライ人への手紙(ヘブル書)」はパウロの著作ではないとされている。 67年にローマで斬首される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○マルコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訳。 ペトロとパウロの弟子。 新約聖書に「マルコによる福音書」がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ルカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医者。 パウロの協力者。 新約聖書に「ルカによる福音書」「使徒言行録」がある。 パウロに付き従って伝道を行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○シメオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルサレム教会第2代主教。 62年に主教ヤコブが没すると、長老たちの全会一致で後継とされた。 クロパの息子。(アルパヨの項参照) イエスの兄弟(従兄弟) 120歳のときに、トラヤヌス帝の迫害の下、ユダヤ提督アッティコに捕らえられ、十字架に磔になり没した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○アルパヨ(アルファイ/クロパ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レビ(マタイの項参照)、小ヤコブ(ヤコブの項参照),シメオン(シメオンの項参照)の父親。 エウセビオス(263年頃~339年5月30日)教会史に引用するヘゲシップス(アンブロシウスと同一人物とみる説もあるらしい)の記事に 『シメオンはイエスの父ヨセフの弟であるクロパの息子であり、イエスが生まれる前に誕生した』 とあるらしい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうしてみると、キリスト教というものは、イエス没後にイエスの親族派(エルサレム教会)と親族ではない派(バチカン/正教会)に分かれたような感じにみえる。 キリスト教団としてのまとまりの中で、一番弟子のペテロ派とヤコブ派(イエスの親族派)という派閥が生まれたのではないだろうか? イスラム教でも似たような話があるので、可能性は高いと思う。 しかし、聖書というものは、記録媒体が貴重な時代から、伝聞、伝文、写本、翻訳が繰り返されてきたため、書簡によって単語や表現が違ったり、誤写、誤訳、改ざんの疑いを持たざるを得ない物や部分があったりする。 そして、写本を現代語訳にするとき、当時の表現や習わしが影響することが多く、曖昧な表記になったりもしたんじゃないかと思う。 例えば 兄弟 という言葉が、古代のユダヤ社会では 従兄弟 とも意味するとのことで、これによって聖書の記述の解釈が訳者によって異なってきてしまう。 イエスの兄弟 の記述が イエスの従兄弟 ともとれるとなると、そりゃあ系図はもう大騒ぎ。なにがなにやら、である。 名前や地名の単語にしても、栄枯盛衰の激しい地域が舞台であるだけに改名した頻度も高ければ、数か国語が飛び交ったりもする。ギシリア語では○○、アラム語では△△。などと。 そんでもって、書簡によって同じ場面を記したと思われる部分の記述が微妙に違ったりするから、訳した人たちはかなり大変だったと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年9月記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエス・キリストの系図 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重いかもしれないけど見たい人はどうぞ アダムとイヴからイエス・キリストまでの系図(別窓表示) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料 聖書 知れば知るほど / 守部喜雅 実業之日本社 ウィキペディア(Wikipedia)フリー百科事典 他にもチラチラいろんなサイトを見させてもらって参考にしました。 もし、 「私が作った(書いた)データを参考にしてるっぽいなあ」 っていうふうに思われた方がいらっしゃいましたら 当サイトのブログにコメントする形でお知らせください。 データ(サイト)の名前とURLと内容をお書きください。 精査したうえで 参考資料元として記載させていただくなりしたいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエス・キリスト 〉〉 聖書 〉〉 〈〈 歴史Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2003~ 黒麒燃魂 All Rights Reserved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||