| 歴史 | ||||||||
聖書 / Testament / the Bible |
||||||||
| ■ | 紀元前4世紀までに書かれた全24巻の書物。(新約聖書は27) ユダヤ教、キリスト教、イスラム教で聖典、啓典、教典とされている。 キリスト教で旧約聖書としているものを、ユダヤ教では聖典、キリスト教では聖典、イスラム教では教典としている。 内容は、天地創造から人類(アダムとイヴ)の登場、そこからノア〜アブラハム〜イサク〜ヤコブ〜モーセ〜ダビデ〜ソロモンへと続く歴史扁と預言書からなる。 書簡の配列は、各宗教によって異なる。 キリスト教で新約聖書としているものを、ユダヤ教では扱わず、キリスト教では聖典、イスラム教では啓典としている。 内容はキリストの行い、教えを弟子たちが書き記したものである。 なお、イスラム教では、新旧の分け方はしていない。 また、外典、偽典などがあり、時代、地域、団体によって使われる教典が違い、大元の教典からいろいろ削られたり、新たに付け足されたりしたのであろう。 |
■ | ||||||
旧約聖書 |
||||||||
| ■ | (神との)古い契約の書 という意味の書物 ユダヤ教、キリスト教の聖典 ユダヤ人(イスラエル人)の歴史書でもあるとも言える。 著者(記者)はほぼその全てが不明 古い言い伝えを編纂した物や、その時代の資料として書かれた物などを 時代時代で再編、翻訳を繰り返して現代に引きつながれてきた。 紀元前4世紀までに書かれたヘブライ語、アラム語の文書群が統一されて「聖書」(全24巻)ができたとみられている。 (ただし、統一する前から「聖書」と呼ばれる文書はあったのかもしれない) 紀元前二世紀(紀元前250年)ごろから 七十人訳聖書(聖書をギリシア語に翻訳した物) の翻訳が始まったとされている。 現存する最古の写本は紀元前一世紀頃の物で、「死海文書」の一部。 創世記 出エジプト記 レビ記 民数記 申命記 ヨシュア記 士師記 ルツ記 サムエル記上 サムエル記下 列王記上 列王記下 歴代記上 歴代記下 エズラ記 ネヘミヤ記 トビト記 ユディト記 エステル記 マカバイ記1 マカバイ記2 ヨブ記 詩編(詩篇) 箴言 コヘレトの言葉 雅歌 知恵の書 シラ書 イザヤ書 エレミヤ書 哀歌 バルク書 エゼキエル書 ダニエル書 ホセア書 ヨセル書 アモス書 アバデヤ書 ヨナ書 ミカ書 ナホム書 ハバクク書 ゼファニヤ書 ハガイ書 ゼカリヤ書 マラキ書 カトリックとプロテスタントの旧約聖書は上記で構成されている。 赤文字はカトリックでのみ含まれる。 ユダヤ教、正教会では、また違った構成となっている。 |
■ | ||||||
旧約聖書 家系図の不思議 |
||||||||
| ■ | 聖書において、人類の始祖(またはユダヤ人の祖)はアダムだとされている。 神(ヤハウェ)は天地創造の後に、地面の土を使って神に似た姿の人間(アダム)を作った。 エデンの園(楽園)にその人間を置き、 「“善悪の知識の木の実”以外の木の実は食べても良い」 と告げる。“善悪の知識の木の実”を食べると死んでしまうという。 |
■ | ||||||
聖書によると、人類は猿から進化したのではなく、人として神に作られている。 または、神が作った唯一の人であるアダムはユダヤ人の祖であって、ユダヤ人以外の人は猿から進化したものであって、初めから人としての生を受けた生き物ではない。また、猿から進化した人がユダヤ人と交配したものも存在する。という思想もある。 アダムの肌の色は何色だったのでしょうかね? 生活拠点を、キリスト教(ユダヤ教)視点で見るか、人類学的に見るかでかわってくるのかもしれない。 キリスト教(ユダヤ教)視点で見れば、エデンの園は中東もしくはその周辺となるのでしょうか。この場合は(あくまでも現代に照らし合わせればですが)褐色の肌色ですかね。 人類学的に見ると、ホモサピエンスの起源はアフリカなので、黒色の肌色となるのでしょうか。 それとも、「神に似せて創られた」のだから、神のごとく神々しく輝く肌色(何色だよ!)なのでしょうか。 美術で見る神様ってほとんど白色ですよね。白人によって作られた歴史だからですかねえ。 ちなみに、イエス・キリストの肌色は、アラブ系だから褐色だったであろうと言われてますね。 これも美術作品では白色の肌色で描かれることが多いですが、それは間違いだといわれてます。 |
||||||||
その後、神は 「人間が一人だけではいけない」 と思って、人間の肋骨を1本取って、その肋骨から女(イヴ/エバ)を作った。 その後、女は蛇(サタンまたはリバイアサン/堕天使、ルシファー)に騙されて、アダムとともに“善悪の知識の木の実”を食べてしまう。 するってえと、自分たちが裸でいるのを恥じらうようになってしまう。恥ずかしいのでイチジクの葉で隠した。 神がエデンの園を歩いていると、二人が隠れるのが見えたので、なぜ隠れたのかを訊ねると、 「裸なので隠れた」 アダムはそう答える。 神は、 「“善悪の知識の木の実”を食べたのか?」 と訊ねる。 アダムは、 「女だけが食べた」 と答える。(初めての嘘、初めての罪) 神は、この件に関わった三者に罰を与えた。 ・アダムに労働を課し、 ・女に妊娠と出産の苦しみを与え、 ・蛇を腹ばいの生き物に変えてしまう。 そして、アダムと女に衣を与えてエデンの園から追放。(失楽園) アダムは女をイヴ(エバ)と名付け、移り住んだ地で子を作ります。 神は、エデンの園の東にケムビム(智天使)と煌めき回る炎の剣を置いて守らせ、人が再びエデンの園に立ち入れないようにしました。 |
||||||||
神の手により、まず男(アダム)が作られ、男の体の一部(肋骨)から女(イヴ)が作られた。 のですが、 創世記の記述 「神は神に似た形に男女を創造した」 という部分を 「神は、神に似た形にアダム(男)とリリス(女)を創られた」 と解釈するというものもあるそうで、イヴよりも先にアダムには妻がいたというのです。 アダムとリリスは同時に創られ、エデンで暮らします。 しかし、アダムと同等の存在であるリリスは、性行為のときにアダムの下になることを嫌がってアダムの前から逃げ出しました。 孤独になってしまったアダムのために、神はアダムの肋骨からイヴを創り、アダムとイヴは夫婦となります。 アダムの前から姿を消したリリスですが、 その後、夜の悪霊(サキュバス)となり、アダムとの間にできた子ら(リリン)も悪霊となります。 そして、悪魔(または死をつかさどる天使サマエル)の妻になります。(『ベン・シラのアルファベット』という文献) そうして、アダムとイヴの楽園(エデン)生活が始まるのですが、二人は神の言いつけを守れなかった。 なぜ神は“善悪の知識の木”をエデンの園に放置したのでしょうか? 人間を試したのでしょうか? 一つだけ手を出してはいけないものを、あえて手の届くところに置いておく。 「それは触っちゃだめよ」 と言われれば、触りたくなってしまうのが性というものである。 他にいっぱい食べるものがあるとは言え、いつしか 「神様はあれを食べるなって言ってたけど、どんな味がするんだろう?」 ってなことを思ってしまうものだと思う。 「でも、食べたら死ぬって言ってたしなあ。死ぬのは嫌だから我慢するか」 ってなもんで、耐えてるうちに気にしなくなる・・・か、自殺行為に走ってしまうか。 神様もさぁ“善悪の知識の木”を排除しといてくれればよかったんだよね・・・。 アダムとイヴは、蛇に騙され“善悪の知識の木の実”を食べてしまいました。 ここでもまた、「な〜んで神様は蛇を放置していたんだろう?」という疑問が出てきます。 そして、“善悪の知識の木の実”を食べてすぐ死ななかったということは、食べたことによって寿命が生まれたということで、もし“善悪の知識の木の実”を食べなければ不死だったということだろうか? しかし、エデンの園には“生命の木”というのもあって、この実を食べると「神のように永遠の命が得られる」ということなので、もともと寿命はあったのかもしれない。 ただ、神は「“生命の木の実”を食べてはいけない」とは言ってないので、アダムたちはすでにこれを食べていたのかもしれない。“生命の木の実”は食べ続けることで「神のように永遠の命が得られる」という果実なのかもしれない。 “知識の木の実”を食べたらエデンの園から追放する。そうなればもう“生命の木の実”は食べられなくなるのでいずれ死にますよ。 ということなのかもしれない。 神は、アダムと女に知恵を与えたくなかった。永遠の命と知恵を人間が持つことを許さなかった。だから、“善悪の知識の木の実”を食べてしまった二人を“生命の木”と“知恵の木”があるエデンの園から追放したのである。 もしかすると、“善悪の知識の木の実”も“生命の木の実”のように食べ続ければ知恵・知識が次々とあふれ出てくるのかもしれない。 “善悪の知識の木の実”を二人が食べてしまったことを知った神は言う。 「人は我々の一人のように善悪を知るものとなった。“命の木”からも取って食べ永久に生きるかもしれない」 だそうな。 ということは、 ●「人は我々の一人のように」 神もしくは神の存在に近しいもの(善悪を知るもの/天使か?)が複数人いること、 ●「“命の木”からも取って食べ永久に生きるかもしれない」 二人は、“命の木の実”をまだ食べていなかった。(食べてはいけないと言われていなかったのに) が明らかになる。 食っときゃあよかったのにね〜 エデンの園の東にケムビム(智天使)と煌めき回る炎の剣を置いて守らせた ということは、アダムとイブはエデンの園の東へ追放されたということですね。 |
||||||||
エデンの園を追放(失楽園)されたアダムとイヴ(エバ)は、カイン、アベル、セト(セツ)の3人の子を作る。(偽典と呼ばれる「ヨベル書」では、息子30人、娘30人をもうけたとされる) 長男のカインは弟のアベルを殺害(人類初めての殺人)してしまう。カインは神から悔い改めるよう迫られるが、応じることなく神に対する信仰を捨ててしまう。 カインはノドの地に追放されます。 カインはノドの地に町を作り、そこをエノクと名付けました。エノクとはカインの息子と同じ名です。 |
||||||||
カインにはエノクという息子がいました。 息子がいたということは、妻がいるはずです。 偽典「ヨベル書」では妹のアワンが妻ということになっています。つまり近親相姦。 ま、そりゃあ、アダムとイヴとその子供たちしか人類がいないわけですから、兄弟と姉妹、父娘、母息子で子づくりしなけりゃ孫の代はできませんわな。 孫同士だといとこ婚なので、現在の日本ではギリ許される範囲となります。(いとこ婚は危険もないわけではないけれど、血筋の能力値を高める可能性のある血縁婚だという噂もあるそうな・・・) ちなみに、モーセの時代の律法以降、現在のキリスト教でも近親相姦は禁じられています。 って、イヴはアダムの肋骨から作られているわけなので、アダムとイヴの夫婦は究極の近親婚と・・・いえるのかも。 |
||||||||
カインとセトの2系統(「ヨベル書」では息子・娘とも30人となっているので、30系統なのかも?)で子孫を繁栄させていく人類。 聖書によると、この時代の人々は、現在よりも長寿だったらしいので、ものすごい勢いで人は(近親相姦で)増え続けていったと思われる。 |
||||||||
どれくらい長寿だったのかというと・・・ |
||||||||
聖書に記されている長寿の人たち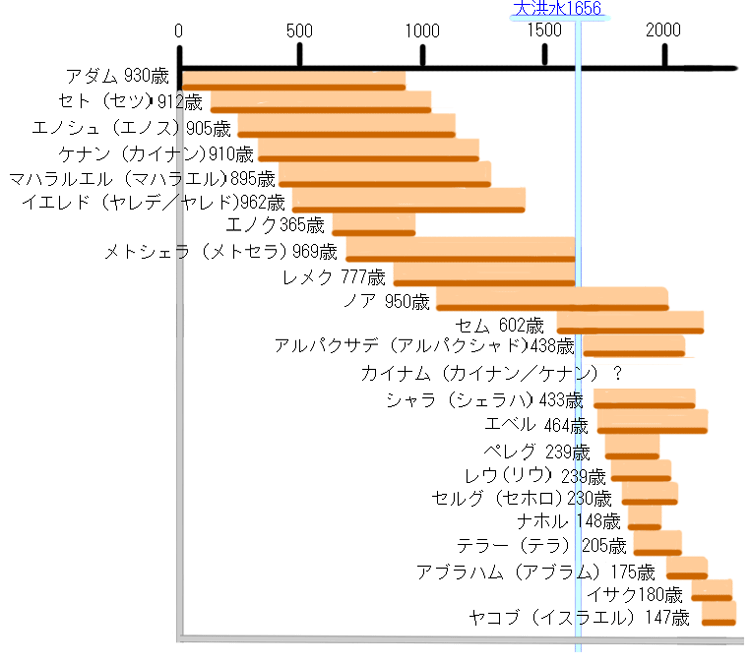 |
||||||||
イヴの寿命の記述はありません。 アルパクサデ(アルパクシャド)の下のカイナム(カイナン/ケナン)ですが、「ルカによる福音書」に「シェラの父、アルパクシャドの子」と記述されているが、誤写ではないかとも言われています。寿命も不明。 「創世記」では、カイナム(カイナン/ケナン)を挟まず、アルパクサデ(アルパクシャド)からシェラへと繋がっていきます。 それにしても、ノアさんってば、10世代(9世代)後のテラーにまで面識あるんですね。恐ろしい族長っぷりが想像できますなぁ。途中で隠居とかしてるんでしょうけど。 長寿といっても、肉体の老化スピードしだいでだいぶん変わってきます。 現代の老化スピードと同じなら、70歳〜100歳で自立した生活は送れなくなります。(個体によって差はあると思いますが) ノアは950歳まで生きてますが、後期の850年以上を寝たきりとか、介助されたりして生きたわけではありません。なにせ、500歳ごろ(もしくは400歳ごろ)に息子のセムをもうけていますから。 そこから考えると、働き盛りの肉体の時期が長いという、一番理想的な長寿だったのかもしれません。 そんな長寿能力を駆使して(たぶんw)産めよ増やせよ人類は反映していきます。 しかし、せっかく(近親相姦も駆使して)人口を増やしていった人類に対して、神はリセットを掛けます。 大洪水です。 神からの啓示を受けていた(アダムから数えて10代目の)ノア(と妻エムザラ。息子3人とその妻たち)だけが助かります。(ノアの箱舟/方舟) ノアは、神の啓示により造った箱舟(方舟)で家族とともに大洪水を生き延びます。それは、ノアが600歳(500歳という説も)のときに起きたと記されています。 〜世界の各地に似たような伝承があることから、神からの啓示を受けて助かったのはノアの家族だけではなく、複数いたとする説もある〜 アダムとイヴの系譜は一旦リセットされていまい、ノア(とエムザラ)を祖(もしくはノアの息子3人とその妻たちを祖)として、人類の補完(繁栄)計画はやり直しとなります。 |
||||||||
ノアの息子3人。セム、ハム、ヤフェテ(ヤペテ)にはそれぞれ妻がいた。 その3人の妻たちは誰の娘なのかの記載は見当たらないが、アダムとイヴの子孫であることは間違いない。(だって、二人から人類は始まっているのだから) 大洪水で生き残ったのは男4人、女4人。 この8人(身持ちが堅ければ4組)の交配で再出発。産めよ増やせよ人類増員作戦再発動となります。 そして、 その後の婚姻は、ノアの孫同士になる可能性は高い。 繰り返しですが、 いとこ婚は、現在の日本でギリ許される範囲。(いとこ婚は危険もないわけではないけれど、血筋の能力値を高める可能性のある血縁婚だという噂もあるそうな・・・) ちなみに、モーセの時代の律法以降、現在のキリスト教でも近親相姦は禁じられています。 大洪水でおそらく、カイン系統(と他の30名ずついたらしい兄弟姉妹)の人々は全滅したと思われます。 なので、トバル・カイン(製鉄技術者の祖)、ヤバル(遊牧民の祖)、ユバル(音楽家の祖)も失われたはずです。 その技術が、ノアとその妻、ノアの息子とその妻たちの誰かに伝えられていた可能性はあるかもしれませんけど、そうでないなら、ノアの子孫がまた一から開発したということになりますわな。 |
||||||||
ノアの子孫は増え続け、文化・文明を築いていきます。 その中で、天に届こうかという塔を建てる人たちが出てきて、又も神の怒りを買ってしまいます。 塔を破壊され(バベルの塔)、同じ言葉を話せなくさせられて世界へ散らされてしまいます。 このことが原因で、世界には言語の違いができたと言われています。 |
||||||||
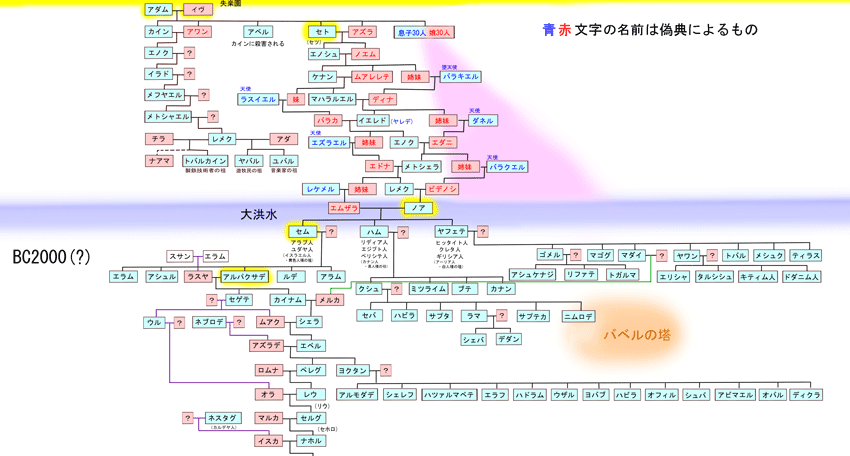 |
||||||||
ノアから数えて10代目にアブラハムという人物が産まれます。 このアブラハムがイスラエルの祖(セム系)と言われています。 アブラハムの孫のヤコブの子らがイスラエルの(12)部族(支族)の祖となります。 ヤコブの息子ヨセフが、兄弟たちによってエジプトに売り飛ばされるが、ヨセフはエジプトの地で頑張ります。 その後、イスラエルの民は飢餓に瀕し、食料を求めてエジプトへ行きます。 エジプトで出世していたヨセフは、家族(自分を売り飛ばした兄弟も)をエジプトへ呼び寄せます。 こうして、イスラエルの民はエジプトの地で重労働を課せられながら(奴隷?)も生きていきます。 |
||||||||
エジプトでイスラエルの民は奴隷として扱われていたのか? 売り飛ばされてきたヨセフが高官になれたり、モーセがファラオ(エジプト王)の娘に拾われ息子となったり(養子?)と、イスラエル人だからといって無碍にされたわけではないような気がします。 移民だからといって、それほど厳しい条件での生活ではなかったのではないでしょうか? |
||||||||
エジプトに移住したイスラエルの民の中から、ヤコブの子レビの曾孫モーセという指導者が生れ、イスラエルの民はエジプトから出ていきます(出エジプト)。 |
||||||||
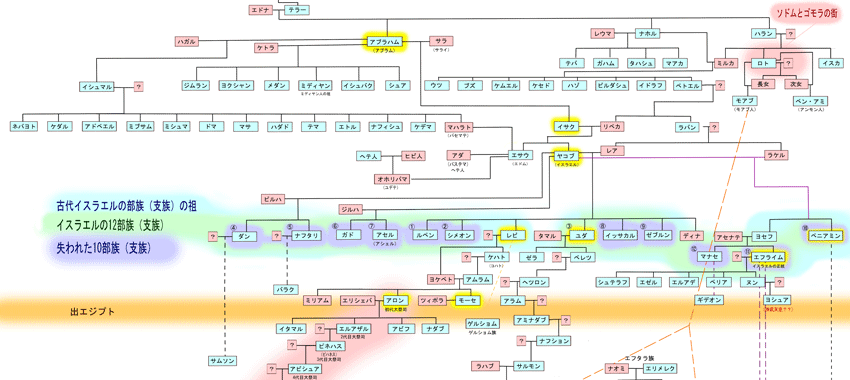 |
||||||||
エジプトから出たイスラエルの民は、モーセの死後に指導者を継いだヨシュア(ヨセフの曾孫)によってカナンの地(約束の地)を奪還。 |
||||||||
指導者ヨシュアの下に(神武天皇??)と書かれているのをお気づきでしょうか? 日ユ道祖論 というものがありまして、 明治時代に日本に滞在したスコットランド人のニコラス・マクラウドという人が 「日本とユダヤは同じ先祖を持ち、日本人とはイスラエルの失われた10支族のひとつである」 という論を唱えたことに始まる。 そこから、日本とユダヤの相似点や伝承を見つけては 「日本人は失われたイスラエルの10支族の末裔だ」 「イスラエルの失われた10支族の一部は日本にやってきていた」 という説が次々と唱えられている。 日本とユダヤの相似点や伝承 「天皇史は聖書の記述に当てはまるところがあり、エフライムの孫でモーセの後を継いで指導者となったヨシュアは神武天皇に当てはまる」 「イエス・キリストは死なずに(もしくは復活後)日本に渡ってきた」 「日本の伊勢神社の石碑に刻まれた裏家紋の篭目紋は、イスラエルの国旗でも描かれているダビデの星(六芒星)と同一である」 「カタカナとヘブライ文字は似ている(関連性がある)」 「大和言葉とヘブライ語は似ている」 「日本の神輿(山車)は、契約の箱(失われたアーク)を模したものである」 「ユダヤ教徒が祈りの時にヒラクティリー(テフィリンを額に着け角笛を吹く姿は、日本の修験道者(山伏)の姿と酷似しており、それは他に類似がない」 「現在の青森県三戸郡新郷村大字戸来にイエス・キリストの墓がある。 イエスは21歳の時に日本に訪れて修業し、31歳の時にエルサレムに帰って処刑された。しかし、処刑されたのは身代わりになった弟のイスキリで、イエス(のちに十来太郎大天空と改名)は日本に戻って戸来村(現在の新郷村)で106歳まで生きた。 新郷村にある二つの墓は、イエスとイスキリの墓だとされている。 イエスとその従者たちの子孫が日本人と同化し、その文化、思想は日本に溶け込んでいる」 などなど。 確かになぁ〜そうかもしれない。 と、思ってしまう説もあったりしますけど、遺伝学的(DNA)には日ユ同祖論の信憑性は低いそうです。 日本人の祖先がユダヤ人というのはあり得ない話。 ユダヤの支族が日本にやってきたというのも可能性は低い。 ユダヤの支族の一部の人が、その伝承の記憶を持って日本にやってきて(渡来)日本人と同化した。 というふうに私はみてます。 |
||||||||
サウルのイスラエル建国からダビデ王へ。 |
||||||||
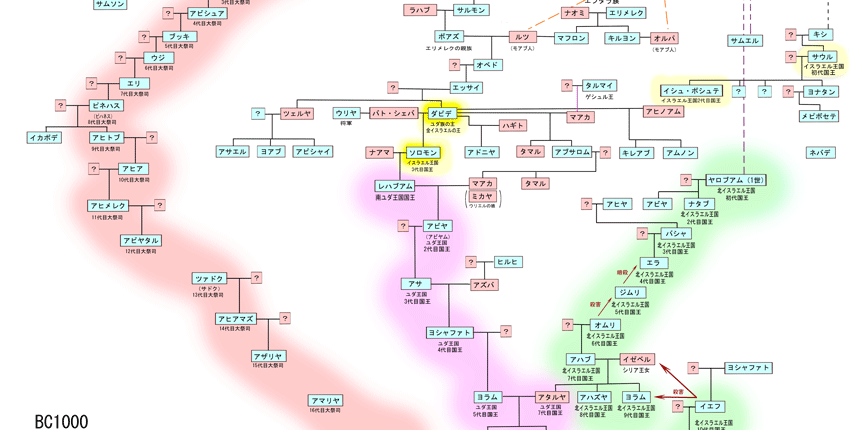 |
||||||||
ソロモン王を経て、イスラエル王国は、北イスラエルと南ユダに割れます。 |
||||||||
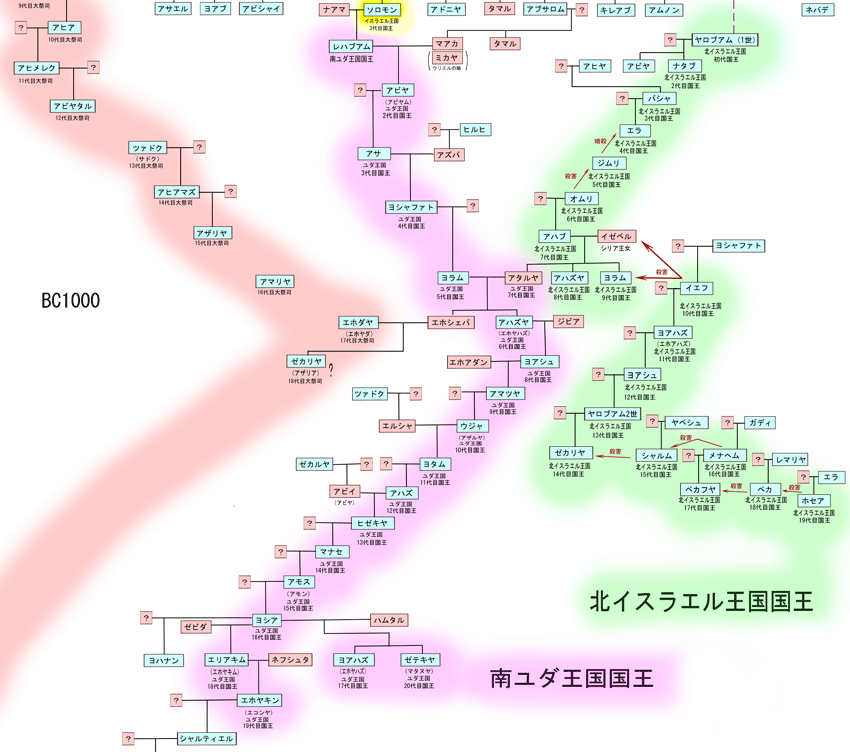 |
||||||||
そして、ダビデ王(ユダ族)の血を継ぐヤコブの婚約者のマリア(マリア自身はレビ族の血{大祭司の血筋}を継いでいる)が処女懐胎し、イエスを降誕する。 |
||||||||
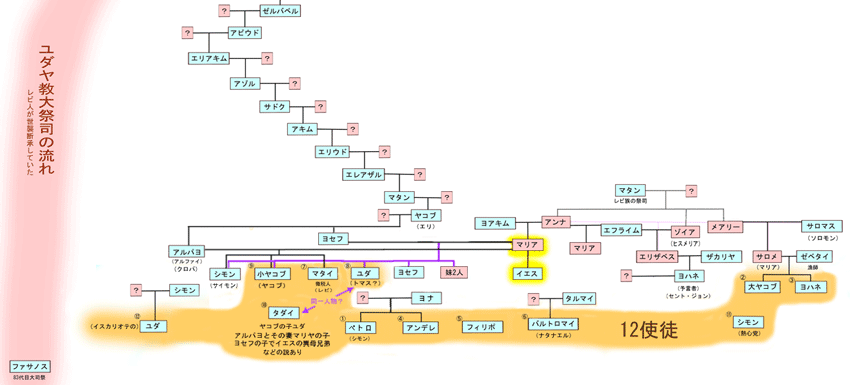 |
||||||||
そして、新約聖書ではイエス・キリストの12使徒たちからの伝承を軸に、イエスの奇跡や宣教を記している。 アダムとイヴからイエス・キリストまでの系図(別窓表示) |
||||||||
新約聖書 |
||||||||
| ■ | (神との)新しい契約の書 という意味の書物 紀元1世紀から2世紀にかけて、キリスト教徒たちの手によって書かれた文書。 マタイによる福音書 マルコによる福音書 ルカによる福音書 ヨハネによる福音書 使徒言行録 ローマの信徒への手紙 コリントの信徒への手紙一 コリンの信徒への手紙二 ガラテヤの信徒への手紙 エフェソの信徒への手紙 フィリピの信徒への手紙 コロサイの信徒への手紙 テサロニケの信徒への手紙一 テサロニケの信徒への手紙二 テモテへの手紙一 テモテへの手紙二 テトスへの手紙 フィレモンへの手紙 ヘブライ人への手紙 ヤコブの手紙 ペトロの手紙一 ペトロの手紙二 ヨハネの手紙一 ヨハネの手紙二 ユダの手紙 ヨハネの黙示録 新約聖書は、上記によって構成されている。 そのほか外典と呼ばれるものもある。 |
■ | ||||||
バビロン / バビロニア / メソポタミア |
||||||||
聖書を読んでいるとバビロン(バビロニア)を忌み嫌っているのかな?と感じる部分が多々ある。 メソポタミアの歴史を見てみると BC6000年頃…新石器文化が花開き始める。 BC5500年頃…シュメール人によって農耕が開始される。 BC4000年頃…都市が形成される。 BC3500年頃…文字(ウルク古拙文字)が発明される。 BC3100年頃…シュメール人による都市国家が発達。 BC2700年頃…ウル、ウルク、ラガシュなど多数の都市国家が形成される。 BC2334年…アッカド帝国がメソポタミアを統一。 BC2300年頃…アッカド帝国の街としてバビロンができる。 BC2154年…ウル第三王朝(ウル・ナンム王)がメソポタミアを支配。 BC2004年…ウル王朝が消滅し、イシン、ラルサ時代が始まる。 BC19世紀頃…古バビロニア王国第6代目王ハンムラビがバビロンを大都市に造り替える。(メソポタミア南部がバビロニア地方と呼ばれるようになる) BC1750年…ハンムラビ王がメソポタミアを征服。 BC1595年頃…現在のトルコにあったヒッタイト王国(鉄の精製技術を持っていたとされる)が古バビロニア帝国を滅ぼす。 BC1400年頃…セム人系のアッシリアが独立。 BC13世紀…アッシリア帝国がバビロンを占領。 BC1200年頃…ヒッタイト帝国滅亡。(原因は「海の民」による侵攻、食糧難などが挙げられている) BC11世紀…アッシリアが勢力拡大。(鉄器の使用) BC7世紀…アッシリア帝国がメソポタミアを支配。 BC722年…アッシリア帝国による北イスラエル王国の滅亡。 BC671年…アッシリア帝国によるエジプト支配。 BC612年…新バビロニアとメディアの反撃により、アッシリア帝国の首都ニネヴェ(空中庭園があったとされる)陥落。 BC609年…アッシリア帝国滅亡。新バビロニア(メソポタミア)、メディア(イラン高原)、リュディア(小アジア)、第26王朝(エジプト)の四帝国時代となる。 BC593年…南ユダ王国が新バビロニアに侵攻。反撃した新バビロニアに南ユダ王国の王族が拿捕されバビロンに送られる。 BC586年…南ユダ王国が再び反乱。またも反撃・鎮圧され、ユダヤ人は新バビロニアのニップール付近に強制移住させられる。 BC539年…アケメネス朝ペルシア(キュロス2世)が新バビロニアを滅ぼす。 BC331年…マケドニア王国のアレクサンドロス3世がバビロンに入城。(ペルシア支配の終焉) BC323年…アレクサンドロス3世の死去によりマケドニア帝国は瓦解していく。 BC141年…パルティアによる支配。 AD116年…ローマ帝国のトラヤヌスによって占領。 AD117年…トラヤヌス死亡。 AD118年…ローマ帝国(ハドリアヌス)が撤退したため、再びパルティアが支配。 AD100年頃…アッシリア人、カルデア人が消えてユダヤ人が残る。(バビロニア崩壊) AD230年…ローマ帝国との度重なる戦いのために国家が疲弊していき(と、みられているが、パルティア滅亡の真因は不明)、パルティアは滅亡し、サーサーン朝がメソポタミアを支配する。 AD636年…イスラム帝国による支配。 AD1258年…モンゴル帝国による支配。 AD15世紀ごろ…オスマン帝国による支配。 AD1920年…イギリス委任統治領(メソポタミア)となる。 AD1932年…イラク独立。 |
||||||||
メソポタミヤ地域周辺地図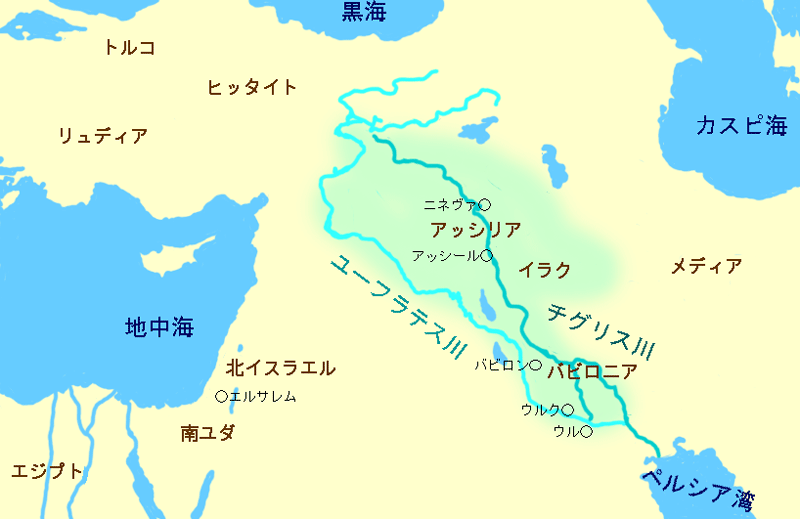 ユーフラテス川とチグリス川に挟まれた地域(■緑色部分)がメソポタミア地域です。 海岸線や川の流れは時代とともに変化するので、現代のマップとは違ってきます。 特にペルシア湾は、川が運ぶ堆積物によって埋まっていったと考えられるので、 時代をさかのぼるごとに河口は川上に向かって伸びていきます。 エルサレムの東側にある湖が死海です。 |
||||||||
おそらく、イスラエルの民がバビロニア&アッシリアに頭を抑えつけられていた時代が長かったことが影響したのではないでしょうか? 北イスラエル王国も南ユダ王国もバビロニア&アッシリアのメソポタミヤ勢力に滅亡させられてます。 |
||||||||
死海文書(死海写本) / |
||||||||
| ■ | 1946年〜1947年に、ヒベルト・クムラン遺跡近くの洞窟の中で壺に入った古代の巻物が発見される。 発見者は、ターミレ族の羊飼いのムハンマド・エッ・ディーブ達。 発見された巻物は、ベツレヘムで古物も扱っていた靴職人のカンドー(シャリル・イスカンダム・シャヒーン)の手に渡り、4つの巻物(『イザヤ書』、『ハバクク書註解』、『共同体の規則』、『外典創世記』)がシリア正教会聖マルコ修道院院長のマー・サムエル(後にアメリカで大主教になる)に買い取られた。 同じころ、ヘブライ大学考古学教授エレアザル・スケーニクとビンヤミン・マザールが発見の話を聞きつけ、カンドーから『戦いの書』、『感謝の詩篇』、『イザヤ書』の断片を買い取った。 1948年4月、スケーニクとアメリカのオリエント学研究所の研究員ジョン・トレバーが、死海周辺で古代の写本が発見されたことを発表。 1954年、サムエルが所有していた4つの巻物が売りに出される。イスラエル政府の意を受けたマザールとイガエル・ヤディン(スケーニクの息子)が匿名で購入。 1967年、ヤディンがカンドーの自宅から『神殿の巻物』を回収。 1949年、巻物が発見された洞窟の場所を特定。2〜3月にかけて数百の写本断片が発見される。 その後、砂漠の遊牧民(ベドウィン)たちが周辺の洞窟を探索し、1952年に新たな巻物、断片が市場に出回る。 フランスとアメリカの考古学者たちが共同で周辺の洞窟を調査。5つの洞窟から巻物、断片が多量に発見される。 その後も、周辺の洞窟から巻物、断片が発見される。 1956年、11番目の洞窟での巻物、断片の発見が最後となる。 写本の公開は遅々としていたが、2009年に第40巻の公開がなされた。 |
■ | ||||||
| あなたは神を信じますか? 信じる人も信じない人もそれは善でも悪でもない。 自己の魂を浄化するために 来世のために 人として生きるために 救いを求めて 神を信じる人は祈る 信じない人だって なんとなく祈っちゃったりする 神は助けてくれるのか? 助けてくれることはほぼほぼない 神を信じる人は言う 信仰を深めなさい もっと神に祈りなさい 神を讃えなさい あなたは神を信じますか? |
||||||||
| 2020年8月記 | ||||||||
参考資料 ウィキペディア(Wikipedia)フリー百科事典 歯の豆辞典 -歯科人類学のススメ- |
||||||||
イエス・キリスト 〉〉 キリスト教 〉〉 〈〈 歴史Top |
||||||||
| Copyright (C) 2003〜 黒麒燃魂 All Rights Reserved | ||||||||